待ちに待った赤ちゃんの誕生だけど、新生児って、ふにゃふにゃしてるし、しょっちゅう飲ませないといけないし、オムツも替えたばっかりなのに汚してるし、しゃっくりもするし、大丈夫?大人が不安になることもいっぱいです。
ここでは、新生児の特徴をみていきましょう。この記事を読めば赤ちゃんへの関わり方が見えてきます。不安になる前に新生児の世界をみてみましょう。
*当サイトは、プロモーションを含みます
新生児期はいつからいつまでか
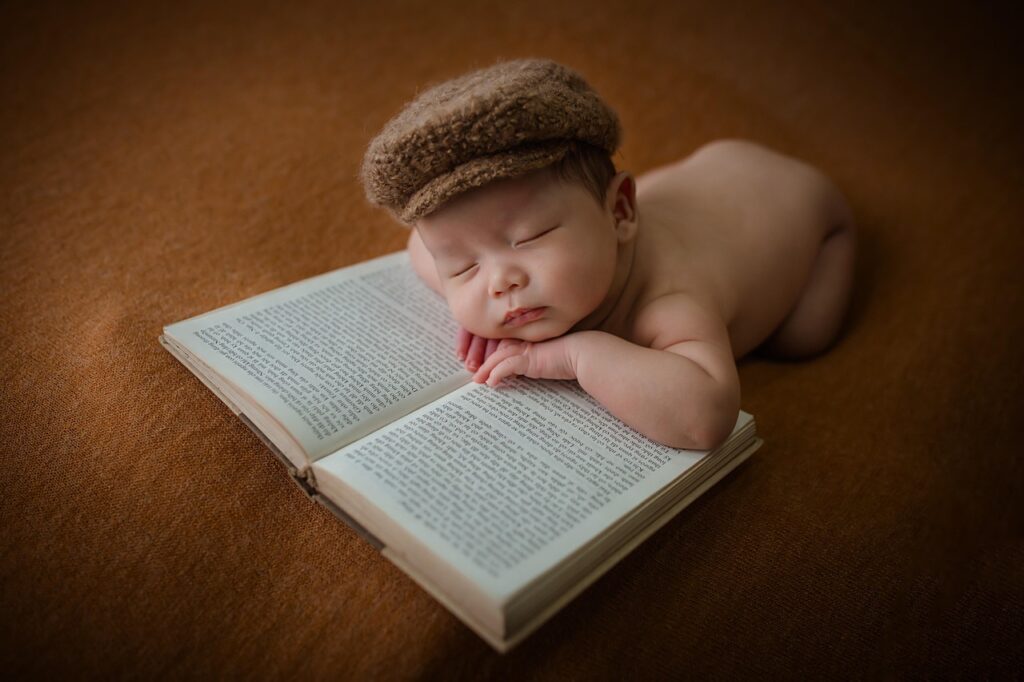
新生児期の定義
「新生児期」とは、赤ちゃんが生まれた日(生後0日)から生後27日目まで、生後4週間以内のことをいい、生後0ヵ月と表記します。
一方で、出生届の提出や日本古来の伝統行事である「お七夜」や「お宮参り」などは、生まれた日を生後1日と数える方法を用いています。出生届は生まれた日を1日として14日以内(国外出生の場合は3ヵ月以内)に提出が必要なので間違えないようにしましょう。(戸籍法第49条)
ママのおなかで過ごした「胎児期」から誕生した赤ちゃんが、「新生児期」に新しい外の世界へ適応していく大切な時期となり、体の適応能力がまだ発達途中で、特に注意なケアが必要な時期です。
乳児期や幼児期との違い

「乳児期」は満1歳未満と定義されます。「乳児健診」や「乳児対象」と記載されている場合は、基本的に1歳未満を対象とされます。
乳児と呼ばれる理由は、漢字の通り「乳」=おっぱいやミルクを飲んで育つ「児」=子です。早くに断乳する場合もありますが、実際に「乳」を飲んでいるかどうかに関わらず、満1歳未満は乳児と表現されます。
「幼児期」は満1歳~小学校就学の始期に達するまでの時期をいいます。
幼の児と書く通り、幼い子ども全般を指すことから、様々な場面で「幼児」という言葉が使用されます。
「乳児」と「幼児」の名称は、未就学児の子どもの月齢を区分する際に使用するものと理解しておきましょう。
「乳幼児期」という言葉もよく耳にしますが、これは「乳児」と「幼児」をまとめて呼ぶときの名称です。「乳幼児期の○○」と表記されている場合は、0歳から小学校就学前の子どもを指します。
新生児期の身体的特徴と発達

新生児期の身体的特徴
新生児期は、体の機能が未熟で、大人とは異なる特徴が多く見られます。 特に呼吸のリズムや皮膚の変化などは心配になることもありますが、多くはおなかの中で羊水に浸かっていた環境から、外の世界への適応の段階でみられる変化です。成長とともに落ち着くものが多いので 赤ちゃんの自然な成長を見守りながら、優しくケアしてあげましょう。
1.体の大きさと体重
- 平均的な体重は2,500g〜4,000g、身約45〜55cm。
- 生後数日で生理的体重減少といわれる、体重減少が一時的に起こります。胎便の排せつや水分蒸散など、飲む量よりも出る量が多いのが原因で、生後3~5日目が減少のピーク、生後7~10日で元の体重に戻っていきます。
2.皮膚の特徴
- 皮膚が一時的に、赤みがかかったり、シワが多かったりします。
- 胎脂(たいし)と呼ばれる、白いクリームのように見えるものが皮膚に付着しています。これは、羊水などから胎児を守るために、おなかの中で胎児の皮膚を覆っていた脂分です。保湿効果や皮膚の防御機能があります。
- 新生児黄疸(しんせいじおうだん)といい、白目や皮膚が黄色くなったように見えることがあります。胎内とは違う環境に適応する際に起こる現象で、新生児の約50%、早産児の約80%にみられます。生理的範囲内であれば問題ありませんが、産院を退院してから突然黄色さが強くなってきたなどの状況がみられる場合は産院へ相談しましょう。
- 新生児落屑(しんせいじらくせつ)といい、皮膚が乾燥して鱗状になり、皮が剥がれ落ちる生理現象で、新生児の90%前後にみられる現象です。羊水の中では、胎脂といわれる油分で覆われ守られていた皮膚が、誕生したことで乾燥することで起こります。

乾燥したりするのは生理現象ですが、最近は、出生早期から正しいアイテムでスキンケアをした乳児は、食物アレルギーやアトピー性皮膚炎などの発症率が極めて低いといわれています。
新生児期からの保湿剤塗布によって、アトピー性皮膚炎の発症リスクが3割以上低下するという研究報告もあります。(参考:国立研究開発法人国立成育医療研究センター)
産院を退院したら、早期から正しい保湿を心がけてあげるようにしましょう。下記の記事も参考にどうぞ。
赤ちゃんのスキンケア~保湿が大切!方法や必要性~【助産師監修】
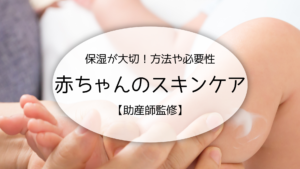
3.頭の特徴
- 頭は体に対して大きく、全身の約1/4を占めます。
- 大泉門(だいせんもん)や小泉門(しょうせんもん)という大人には見られない骨の隙間があります。成長するための隙間で、脳があるので、隙間を指でギューギュー押さえたりしないようにしましょう。隙間は生後1歳6ヵ月頃までに閉じていきます。
- 出産時の産道という細いところを通ってきているで頭の形が少し変形していることがあります。多くは、頭が前後に伸びたような形をしていますが、元に戻るので心配の必要はありません。
4.目の特徴
- ぼんやりと見えており、視力にすると0.01〜0.02程度。
- 明るさや暗さは感じているといわれ、強い光には目を閉じます。
- まだ見えたものを目で追ったり、焦点を合わせることは難しいです。
- 20~50cm程度のところにあるものが一番見えやすく、イメージとしては、おっぱいを飲む体勢のときにママの顔あたりが一番見える感じです。
5.耳と聴覚
- 聴覚は生まれたときから発達しており、おなかの中で聞いていたママの声や胎内音に似た音に安心を感じます。話しかけても反応しないように見えるかもしれませんが、しっかりと聴いて、脳に蓄えていますので、いっぱい話しかけてあげてください。
- 大きな音に驚くモロー反射を示します。
6.口と舌の特徴
- 吸啜(きゅうてつ)反射や探索反射といい、口に入ってきたものを吸ったり、口に何か触れると触れた方向に顔を向けて口を開けたりする原始反射があります。
- 舌を出すことがありますが、これは口周りの筋肉の未発達により自然に出しやすい状況であることや、遊び、空腹のサインなど様々なことが考えられます。
7.手足と筋肉の特徴
- 筋肉がまだ発達していないため、腕はW型、足はM型が新生児の赤ちゃんの基本スタイルです。
- 手は握りしめていることが多く、手の平を刺激するとキュッと握る掌握(しょうあく)反射という原始反射もあります。生後3~4ヵ月頃、遅くても5~6ヵ月頃にはみられなくなるのが一般的です。
- 両脇を支え、足を床につけると左右の足を交互に動かし、歩くような動作をする原始歩行反射がみられ、一般的には生後2ヵ月頃にみられなくなります。
8.呼吸と心拍数
- 呼吸は浅く速い(1分間に40〜60回)ことが特徴。
- 未熟なため呼吸が不規則になることがあり、数秒程度呼吸をとめる「周期性呼吸」と言われる呼吸がみられることがあります。
- 心拍数は1分間に120〜160回と、大人よりも速めです。
9.消化機能と排泄
- 胃が小さく、一度に飲める量が少ないため頻繁な授乳が必要です。
- 生後数日間は胎便(黒っぽい便)を出しますが心配いりません。
- 排尿回数は多く、1日10回以上になることも。
新生児期の発達段階

新生児は、外的な世界に適応しながら少しずつ成長していきます。 まだ意識的な行動は少ないですが、初歩的な反射や赤ちゃんの感覚と親を含む周りの大人との関わりを大切にしていきましょう。 泣き方や動きに注意を払いながら、赤ちゃんのペースに合わせたケアをすることが大切です。
1.身体の発達
- 体重と身長の変化: 生後数日は生理的体重減少がみられますが、新生児の1ヵ月で体重は約1kg、身長は約5~7cm伸びます。
- 初期反射: 新生児には、様々な原始反射がみられます。
2.感覚と認知の発達
- 視覚:ぼんやりと見えており、視力にすると0.01〜0.02程度。明るさや暗さは感じているといわれ、強い光には目を閉じます。まだ見えたものを目で追ったり、焦点を合わせることは難しいが、20~50cm程度のところにあるものが一番見えやすいのが特徴。
- 聴覚: 妊娠7か月頃から、胎内で周囲の音を聞いているといわれ、胎内で聞いていたママや周囲の声、胎内音が心地よく聞こえます。
- 嗅覚・味覚: 母乳の匂いがわかります。また生まれながらに味覚があり、甘味、苦味、酸味、塩味、うま味という5種類の基本味を感じることができます。
- 触覚:五感の中でも最も早く発達し、敏感です。妊娠7週頃には皮膚感覚が発達し始め、10週頃には指しゃぶりの間隔も発達します。肌の刺激は直接脳を刺激するため、スキンシップによって親の愛情を感じ取ったり、幸せホルモンであるオキシトシンを分泌したりします。たくさんスキンシップしてあげましょう。
3.運動の発達
- 頭を少し持ち上げようとする: うつ伏せにすると、頭を持ち上げようとする動きがみられ、一瞬だけ持ち上げることもできます。
- 手足の動きが活発:意図的に動かすことは難しいが、手足はよく動きます。身体の中心(体幹)の方から発達が見られ、徐々に末端(手先や指先)への発達が進みます。
- 寝返りはまだできない:首もすわっておらず、ゴロンと寝返ることはできません。
4.社会性と情緒の発達
- 泣くことで意思表示: お腹がすいた、眠い、暑い、だっこしてほしいなどを表現します。
- 母親の声や顔に反応: 母親の声を認識しており、母親の声がするとピタっと泣きやんだり、動きが止まったりすることがあります。
- 生理的微笑: 意思をもって微笑んでいるわけではないが、無意識に現われる笑顔のこと。眠っているときや授乳後にみられることが多く、生後2ヵ月くらいまでみられます。
新生児期に見られる反射現象
- モロー反射:赤ちゃんが外部からの刺激に対して、意志とは関係なく抱きつくように両手を大きく広げる反射です。大きな音や強い光など起こり、生後4ヵ月頃にはみられなくなります。
- 探索反射(ルーティング反射):口や唇に何かが触れた時、触れた側に顔を向ける反射です。乳首を見つけるために備わった本能的な反射で、顔を向けながら口を開けることもあります。生後5~7ヵ月頃にはみられなくなります。
- 吸綴反射:唇や口腔内に触れると、唇や舌を使って強く吸う動作をする反射で、母乳を飲むための一連の反射の一つです。生後4~6ヵ月くらいまで続きます。
- 手掌把握反射:手の平に何かが触れるとキュッと握るような動きをする反射で、生後3~4ヵ月頃までみられます。
- 足底把握反射:足の指の付け根部分を押さえると、キュッと握るような動きをする反射で、生後10ヵ月頃までみられます。
- バビンスキー反射:足の裏の外側(小指側)を、かかと側からつま先へさするように刺激すると、足の指を開く反射で、生後すぐから1~2歳までみられることがあります。
- 自動歩行反射:足の裏が床につくように立たせるように支えると、歩いているような動きをする反射で、生後2~3ヵ月頃までみられます。
新生児期のお世話の仕方

授乳は2~3時間ごとに行う
新生児は、胃の容量も少ないため頻回に授乳が必要になります。夜間も関係なく、授乳が必要です。
特に、母乳の場合は消化が早いため1~2時間毎に授乳しているという場合も多くあります。ミルクの場合は、3~4時間毎になります。ミルクは消化に時間がかかるため、母乳より授乳間隔があきます。
ミルクのほうが長く寝てくれるならミルクといわれることもありますが、母乳の消化が早いということは胃への負担が少ないということでもあるので、必要ないミルクを寝かせるためだけに足すのはやめましょう。
母乳やミルクは欲しがるだけ与える?
基本的には、欲しがるだけ与えてOKですが、いくつか注意点もあります。
母乳の場合は、欲しがるタイミングで飲むだけ与えてOKです。母乳のカロリーは一定ではなく、授乳中も赤ちゃんへ与えるカロリーが変わるなど調整されます。胃への負担も考えなくて大丈夫。
ミルクの場合は、授乳間隔3~4時間で、与える1回量も規定量を大幅に超えないように与えてあげてください。飲みすぎが消化不良の原因になることもあります。ミルクをたくさんのお湯で薄めに与えたりするのもやめましょう。バランスが崩れる原因になります。
おむつが湿ったらすぐに交換する
新生児は排せつの回数が多くなりますが、汚れたらその都度、おむつ交換をしてあげてください。1日の交換回数は10回以上になることも多いです。
基本的には、汚れに気づいたらすぐ交換です。紙おむつの場合、「もったいないから、もう1回くらいおしっこを吸わせよう!」と考えがちですが、交換してあげてください。清潔なものを身につける『快』の間隔を覚えます。
赤ちゃんの皮膚は、つやつやで綺麗ですが、実は薄くてデリケートな肌をしています。肌トラブルを避けるためにも汚れている場合は交換してあげましょう。
室温は20~25度に保つ
赤ちゃんは、体温調節が苦手です。寒いところにいると体温は下がるし、暑いと体温はあがります。手足で温度を確めるのではなく、首の後ろや背中など、身体の中心部に触れてみて、冷たくないか暑くないか確かめるようにしましょう。
部屋の温度は寒すぎず、暑すぎずで調整してあげてください。基本の室温は20~25度と言われていますが、25度でも太陽のあたっている場合は暑いかもしれませんし、20度でも風があたっていたりすると寒いかもしれません。
授乳後は必ずゲップをさせる
新生児は授乳の際に、空気も一緒に飲み込んでしまいがちです。空気を飲み込んだままにしていると、赤ちゃんが不快に感じる原因になったり、吐き戻しの原因になったりします。
授乳したあとは、縦抱きを行いゲップがでるように背中を優しくトントンするか、さすってあげましょう。5分程しても出ないなら、無理に出さなくてもOK! 少し頭を高くして寝かせてあげると吐き戻し防止になります。
しゃっくりをよくする
新生児は、横隔膜などの臓器が未発達でデリケートなため、少しの刺激でも、よくしゃっくりをします。
たとえば、授乳でおなかが膨れた刺激で横隔膜が刺激されたり、身体が冷えたことで横隔膜が縮んだり、便秘したりすることでも、しゃっくりが起こります。
基本的には自然にとまるので、気にしなくて構いませんが気になる場合は、げっぷを出すようにトントンしてあげたり、冷えたりしている場合は服を1枚着せてあげたり、おむつが濡れていることで冷えることもありますので、オムツ交換してあげたりしましょう。
受診が必要な場合は、2~3時間しても治まらない場合や、しゃっくりの他にもぐったりしていたり気になる症状が併せてあるときには小児科に相談してみましょう。
夜間や休日などで病院が閉まっている場合は、子ども医療電話相談を利用してみましょう。子ども医療電話相談は、厚生労働省が実施している事業の一つで、小児科医や看護師が相談に乗ってくれるので覚えておきましょう。
新生児期の睡眠のポイント

快適な環境を整える
室温は20~25℃、湿度は40~60%、エアコンの風や直射日光などは、あたらない場所に寝かせるようにしましょう。
夜間も授乳が必要な新生児ですが、夜は室内を暗く、朝になったらカーテン等は開けて明るくしましょう。昼夜の区別がつきやすくなるため、生活リズムをつけていきやすくなります。
安全なベビーベッドを使用する
赤ちゃんの周りには、タオルなど顔にかぶってしまうようなものや、誤って口に入ってしまうようなものは何も置かず、ベビーベッドに寝かせてあげましょう。新生児は寝返りをしませんが、手足をバタバタすることで想像以上に動きます。ベビーベッドから離れる場合は、ベッド柵を必ずあげてください。
ベビーベッドを使用しない場合は、周囲に何も置いていないか注意し、赤ちゃんの兄姉やペットに踏まれたりする位置ではないか注意することが大切です。
寝かしつけのルーティンを作る
新生児に昼夜の区別はないため、夜は寝るという概念がありませんが、「夜は静かで暗い」「お風呂のあとは寝る」など毎日同じ流れで、繰り返し行うことで、習慣化されていきます。
寝かせる1時間程前から、お風呂に入れる→授乳しゲップさせる→おむつ替え→スリーパーおくるみを着せてもよい→スキンシップで抱っこしながらトントンする→抱っこしながら、絵本の読み聞かせや音楽を聞かせたりもよい→眠そうになってきたら布団におろしてトントンする
ルーティン化は数日など短い期間ではできませんが、根気よく赤ちゃんの様子をみながらおこないましょう。
乳幼児突然死症候群(SIDS)を防ぐため仰向けで寝かせる
寝かせるときには必ず仰向けで寝かせてください。原因はわからないとされていますが、うつぶせ寝や、やわらかい寝具、周囲の大人の喫煙がリスクになります。
詳細を知りたい方は、こども家庭庁のホームページをご参照ください。→こども家庭庁 https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/kenkou/sids
新生児期の健康対策
ワクチン接種スケジュールを確認する
予防接種の種類、内容、接種推奨時期などは決められており、一番早いもので百日せきなどを含む5種混合ワクチンの接種が、生後2ヵ月から始まります。(B型肝炎等は除く)
赤ちゃんのワクチン接種は、半年ほどで15回以上にもなりますので、ワクチンの推奨時期になれば効率よく接種していくことができるようスケジュールを組んでおきましょう。
生年月日を入力することで、ワクチンスケジュールが組めるところもありますので、気になる方は次のリンクへどうぞ。⇒ワクチン.net マイスケジュールを作ろう
手洗いを徹底して感染症を予防する
新生児のお世話をする際、特に授乳、オムツ替えの前後には必ず石鹸で手を洗うか、アルコール消毒するようにしましょう。
新生児期に関するよくある質問
新生児の沐浴はいつまで続けるべき?
生後1ヵ月(4週間)を迎えるまで、または、おヘソが取れて、おヘソが完全に乾くまでです。おヘソが取れたところから雑菌が入って、感染を起こすのを防ぐためです。
確実なのは、産院で受ける1ヵ月健診で「お風呂に一緒に入って大丈夫か?」を確認しましょう。健診では、赤ちゃんのおヘソだけでなく、全身チェックしているので、健診でOK!もらえば安心です。
赤ちゃんの沐浴について気になる場合は、次の記事も参考にしてください。

新生児の黄疸はいつまで続く?
新生児黄疸とは、赤ちゃんの白目や皮膚が黄色くなってくる現象です。ほとんどの場合は、生理的(問題のない)黄疸ですが、生理的範囲を超えないか産院に入院中は必ずチェックがされています。
生後2~3日から始まり、4~6日目にピーク、その後は下がり、通常は10日~2週間以内に消失します。ほとんどの場合は問題ありませんが、退院してからも黄色さが強くなってきたり、長く続く場合は必ず産院へ相談しましょう。
まとめ
新生児との生活は、喜びや感動にあふれながらも、不安や戸惑いを感じることも多いかもしれません。 でも、赤ちゃんの成長は、一日がかけがえのない時間です。
完璧を目指すのではなく、赤ちゃんと一緒に少しずつ学びながら、心地よいペースで過ごしていきましょう。
小さな成長を見守りながら、親子の絆を大切にして頑張ってください。このブログが、少しでも皆さんの育児のお役に立てば幸いです。


コメント