「赤ちゃんの生活リズムが整わないのは、私だけ…?」
そんなふうに不安に思うママやパパはたくさんいます。新生児期は、まだ昼夜の区別がつかず、睡眠・授乳・排せつのサイクルがとても不規則な時期です。
でも大丈夫。これは赤ちゃんの自然な発達の一部なんです。
このブログでは、助産師として多くのご家族をサポートしてきた経験をもとに、赤ちゃんの生活リズムが整わない理由と、少しずつ整えていくためのヒントをわかりやすくお伝えします。
睡眠、授乳、排せつなど、毎日のお世話に役立つ情報をぎゅっとまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。
*当サイトは、プロモーションを含みます
新生児の生活リズムに関する基礎知識新生児の生活リズムに関する基礎知識

新生児の1日のスケジュール
新生児期の赤ちゃんは、実は「決まった時間に起きて寝る」というより、眠ったり起きたりを繰り返すのが普通です。
たとえば…
- 1回の睡眠は30分〜3時間程度と短め
- 授乳は2〜3時間おき(頻回授乳が基本)
- 1日の中で何度も寝て起きるサイクル
まだ昼夜の区別がはっきりしていないため、夜中も何度も起きて授乳やおむつ替えが必要になります。
生活リズムが不規則な理由
赤ちゃんの脳や体は、まだ未熟な状態。
特に体内時計を調整する「メラトニン」というホルモンの分泌が十分でないため、昼と夜の区別がつきにくいのです。おなかの中でも、出生前は20分程度で寝たり起きたりの生活を繰り返していて、出生直後もそれが続きます。
さらに、お腹が空くタイミングや排せつリズムもバラバラなので、生活リズムが不規則になるのは、赤ちゃんの成長過程では普通です。
新生児の生活リズムと睡眠の関係

新生児の理想的な睡眠時間
新生児は1日に合計14〜17時間くらい眠ります。
でも、一気に長時間寝るのではなく、数十分から数時間の睡眠を何回かに分けてとるのが普通です。
新生児の睡眠合計時間は、個体差が大きく、1日20時間以上眠る赤ちゃんもいれば、8時間で足りる赤ちゃんもいると何かの文献で読んだこともあります。しっかり飲んで、体重も増えて、機嫌がよければ、あまり合計時間を気にしないようにしましょう。
昼夜逆転を解決する方法
昼夜逆転は、多くの新生児が経験します。体内時計がまだまだ未熟な新生児、2~3時間おきには起きて授乳を必要とします。
ママ・パパができるポイントは以下の通りです:
- 朝になったらカーテンを開けて、外の光を取り入れる
- 昼間はできるだけ明るい場所で過ごす
- 夜は静かで暗い環境をつくる
- 昼夜の違いを赤ちゃんに伝えるように声かけや抱っこを工夫する
- 沐浴して、授乳したら部屋を真っ暗にして静かな部屋に寝かすなどルーティンをつくる
ただし、すぐに変わるものではないので、焦らず赤ちゃんのペースに合わせてゆっくり整えていきましょう。
新生児の生活リズムと授乳の関係

新生児の授乳の頻度と量
新生児は、2〜3時間ごとに母乳やミルクを飲みます。
量はまだまだ少なく、出生1日目で1回に飲む量は、ビー玉1個ぶんくらい。日に日に、一度に飲める量も増えていきます。
授乳時間による生活リズムの整え方
- 夜、授乳中はできるだけ静かな環境にして、落ち着いた雰囲気を作ることで、自然と夜の時間帯を認識しやすくなります。
- 授乳の間隔をあまり空けすぎないことが大切。空腹になると赤ちゃんは泣いてしまいます。
- 授乳の時間を決めすぎず、赤ちゃんのサインに合わせてあげてください。
新生児の生活リズムと排せつの関係

排せつの回数とタイミング
新生児は1日に何度もおしっこやうんちをします。
特に母乳育児の場合は、頻繁に排せつがあり、赤ちゃんの健康のバロメーターにもなります。
- おしっこは1日に6回以上が目安
- うんちは母乳の場合は1日数回、ミルクの場合は少し回数が少なくなることも
オムツ交換の頻度による影響
オムツは濡れていると赤ちゃんが不快になるため、こまめに交換しましょう。
オムツが濡れていることで赤ちゃんがぐずったり、眠りが浅くなることもあります。
こまめな交換が、赤ちゃんの快適な生活リズムを支えるポイントです。
新生児の生活リズムと発達の関係
感覚の発達による影響
新生児は視覚や聴覚、触覚などの感覚がまだ発達途中。
新しい刺激に敏感で、光や音が強すぎるとびっくりしてしまい、眠りにくくなることもあります。
原始反射による影響
赤ちゃんは生まれつき「原始反射」という体の反応を持っています。
たとえば、びっくり反射(モロー反射)は急な音や動きに反応して手足をバタバタさせるものです。

この反射が起きると、赤ちゃんは目を覚ましやすくなります。
だから、穏やかな環境づくりや、スワドル(おくるみで包むこと)などで落ち着かせることが大切です。
新生児の生活リズムが整わないときの対処法
過ごしやすい環境を整える
- 部屋の明るさや温度を調節する
- 静かで安心できる空間づくりを心がける
コミュニケーションをとる
赤ちゃんは言葉は話せませんが、表情や声で気持ちを伝えます。
やさしく話しかけたり、抱っこしたりすることで安心感が生まれ、リズムも安定しやすくなります。
スキンシップを楽しむ
抱っこや肌と肌のふれあいは、赤ちゃんの心と体の発達を促します。
ママ・パパの体温や声を感じることで、安心して眠れることも多いです。
ママ・パパの身体を休める
生活リズムが整わないと疲れやすいですが、ママ・パパの心身の健康も赤ちゃんのために必要です。
周りのサポートを借りながら、無理せず休みましょう。
新生児の生活リズムに関するよくある質問

夜泣きがひどいときの対処法は?
- 赤ちゃんが安心できるよう抱っこやトントンであやす
- 部屋の明かりを暗めにして刺激を減らす
- 授乳やオムツ替えをチェックし、不快を取り除く
- それでも続く場合は、助産師や医師に相談を
新生児が泣きやまなかったりする際には、次の【寝ない、泣きやまないときの対処法!】の記事も参考にしてください。
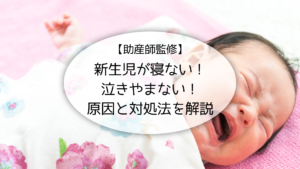
昼間に全く寝ないときの対処法は?
無理に寝かせようとしなくてもいいということは覚えておきましょう。起きて大人しくしているなら、一人にしていても問題ありません。一人にする際にはベッド柵などはあげる、周囲にタオルなど顔にかぶってしまうものもないなど安全な環境は確認しましょう。
- 静かで落ち着いた場所に移動してみる
- ゆっくり抱っこしながら軽く揺らす
- 赤ちゃんの機嫌をよく観察し、無理に寝かせようとしすぎないことも大切
まとめ
新生児の生活リズムはまだ未熟で不規則です。
赤ちゃんの睡眠・授乳・排せつのサイクルを理解し、やさしい環境づくりとコミュニケーションで少しずつリズムを整えていきましょう。
焦らず赤ちゃんのペースに寄り添いながら、ママ・パパも無理せず休むことが、育児を続けるコツです。

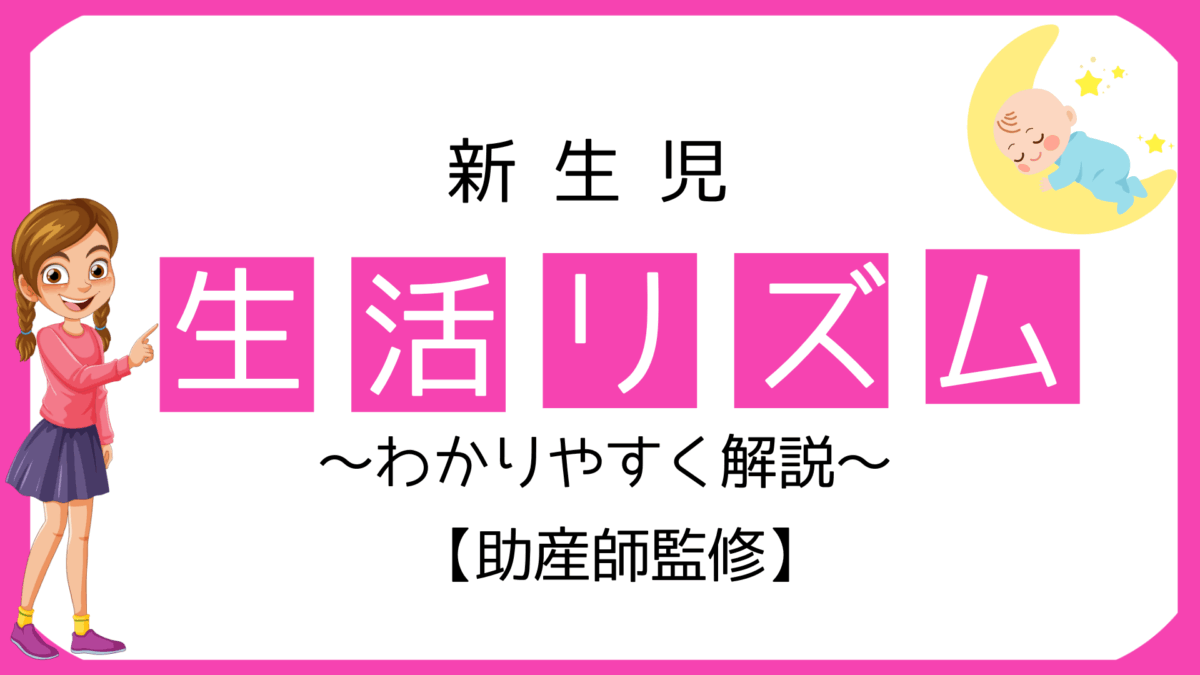
コメント