出産をどこでするかは、妊娠中に悩むことのひとつです。
実家に戻って出産・育児をする「里帰り出産」は昔からよく選ばれてきた方法ですが、最近では「里帰りをしない」という選択をされる方も増えています。
この記事では、助産師の視点から「里帰り出産をおすすめしないと言われる理由」や、「しない場合のメリット」「必要な準備」などをわかりやすくまとめました。ご自身やご家族にとってベストな出産スタイルを選ぶ参考になれば幸いです。
*当サイトは、プロモーションを含みます
里帰り出産をおすすめしないと言われる理由

里帰り出産にもデメリットがあると言われることがあります。デメリットをみてみましょう。
医療設備が整っていない場合があるから
地域によっては、大きな病院やNICU(新生児集中治療室)が少ないことも。
出産は、ママも赤ちゃんも〝命がけ”。出産時に救急の対応が必要になることや、大きな病院への搬送が必要になるということもあります。
ストレスが増える場合があるから
家族との関係性や実家のルールなど、思っていたより気を使ってしまう方もいます。
赤ちゃんを連れて帰った場合、誰がどんな風に手伝ってくれるか、ママ自身が心も体も休める環境にあるかをイメージしてみましょう。
生活リズムや環境が大きく変わるから
「実家だから安心」と思われがちで、実際、実家で心地よく過ごせるママも多いですが、実はストレスになってしまう方がいるのも事実。
「里帰りすれば安心」と一概に言えないのが、今の時代の出産事情です。
大切なのは、自分自身がリラックスできて、赤ちゃんと向き合える環境かどうか。
里帰りするかどうかを決めるときは、実家での生活スタイルを思い描いてみて、「自分が気持ちよく過ごせそうか?」「産後のサポートと、ストレスのバランスはどうか?」といった視点で考えてみると、後悔のない選択ができると思います。
医師との連携がうまく取れない場合があるから
里帰り出産では、妊娠中の健診を受けていた病院と、出産をする病院が変わるというケースがほとんどです。
この「病院の引き継ぎ」がスムーズにいかないと、思わぬ不安やトラブルにつながることがあります。
たとえば……
- 転院先の病院に紹介状や健診データが十分に伝わっていなかった
- 検査や経過観察の内容が病院ごとに異なり、判断が分かれる
- もともとの持病や妊娠中のトラブルについて、新しい病院では把握しきれないことがある
- 慣れない病院で、医師や助産師との関係が築きづらく、ちょっとした相談がしにくいと感じることも
特に妊娠後期に入ってからの転院になるため、引き継ぎのタイミングや情報のズレが起こりやすくなります。
また、出産する病院での健診回数が少ないため、医師やスタッフとの信頼関係が築けず、「なんとなく聞きづらい」「安心して任せられない」と感じる方もいます。
もちろん、転院がうまくいき、安心して出産された方もたくさんいらっしゃいます。
でも「ずっと通っていた病院で出産できたら、もっと安心だったかも…」と感じる方も少なくありません。
医師との関係性は、出産の安心感にも大きく関わるポイントのひとつ。
この点を大切にしたい方には、里帰りをしない選択も、十分に価値のある選択肢です。
里帰り出産をしないメリット

「そのまま自宅で出産・育児を始めたい」という方にとっては、こんなメリットもあります。
同じ病院や産院でケアを受けられる
妊婦健診から出産、産後のフォローまで一貫して対応してもらえる安心感があります。
移動の手間やリスクが少ない
臨月に長距離移動する必要がなく、ママの体にも、おなかの赤ちゃんにも負担がかかりにくいです。
慣れた環境で生活できる
心も体もリラックスしやすく、環境が変わらないので、ストレスが少なくて済むことも。
夫がすぐに育児に参加できる
生まれたての赤ちゃんとの時間を一緒に過ごすことで、パパの育児スイッチも入りやすくなります。一番よく泣いて、授乳やオムツ交換がしょっちゅうで、初めての赤ちゃんに戸惑う時期。パパとの絆を深め、赤ちゃんとパパと一緒に過ごすことは、今後の育児にもメリットが大きいです。
赤ちゃんを迎え入れ、育児を“ふたりごと”にできることは、長い子育て生活のなかでとても良いスタートになりますよ。
里帰り出産をしない場合に必要な準備
産後は、想像以上に心も体も疲れやすく、赤ちゃんのお世話に加えて家事もこなすのは本当に大変。
「ひとりでがんばらなきゃ」と思わず、まわりの力を借りるのは育児の大切な一歩です。サポートしてくれる人がいることで、ママの回復も早まり、赤ちゃんとの時間ももっと穏やかなものになります。
出産後すぐに始まる赤ちゃんとの生活を、ご自宅で無理なくスタートさせるために、周囲のサポート体制をあらかじめ整えておくことがとても大切です。
家族や親せきによる産後サポートの確保
家族や親せきにサポートをお願いできるか、早めに考え、サポートしてもらえそうなら相談してみましょう。
次のようなかたちでのサポートがあると、産後の負担がぐっと軽くなります。
- 数日でもよいので、実母や義母に泊まりがけで来てもらう
- 日中だけでも手伝いに来てもらえるよう予定を組んでおく
- 兄弟姉妹に買い出しや上の子のお世話をお願いする
サポートをお願いする際は、「何を・どのくらい・いつからいつまで」手伝ってもらえるのかを具体的に話し合っておくと安心です。
パパや家族との役割分担

出産後は、赤ちゃんのお世話だけでなく、家事や自分の体の回復にも時間とエネルギーが必要になります。特に里帰りをしない場合、すぐに夫婦や家族だけでの生活が始まるため、誰が何をどこまで担当するのかを、事前に話し合っておくことがとても大切です。
たとえば、こんな分担をイメージしてみましょう
- パパでもできること
・夜間の授乳やおむつ替え(母乳でもゲップや寝かしつけなどで協力可能)
・沐浴や赤ちゃんを抱っこしてあやす
・買い物、料理、掃除、洗濯などの家事全般
・上の子のお世話(いる場合)や保育園の送り迎え - ママが中心になること
・授乳(母乳の場合)や赤ちゃんの体調管理
・赤ちゃんとのスキンシップや成長の記録
・自分の体調管理と回復(無理しすぎないで。授乳を1回誰かにしてもらって、その間寝るだけでもかなり楽になれます) - 同居の家族や親せきがいる場合にお願いできること
・ごはんの支度や片づけ
・洗濯や日用品の買い出し
・赤ちゃんを少しの間見ていてもらう(ママの休憩時間づくり)
ポイントは、「できること・できないこと」を正直に伝え合うこと
「全部ひとりで抱え込んでしまってつらくなった…」という声も少なくありません。
だからこそ、お互いにできること・得意なこと・手伝ってほしいことを、あらかじめ共有しておくことが大切です。
紙に書き出して分担表を作っておくと、あとで混乱しにくくなりますよ。
産後は体力も心も不安定になりやすい時期。パパや家族としっかり連携することで、「チーム育児」の第一歩を安心して踏み出すことができます。
陣痛タクシーの登録
妊娠中に事前登録をしておくと、陣痛が来たときや破水したときにすぐに迎えに来てくれるサービスです。通常のタクシーと違い、運転手さんが妊婦さんの対応に慣れていたり、防水シートを用意してくれているなど、安心して乗車できるよう配慮されています。
陣痛タクシーのメリット
- 24時間対応の会社が多く、夜間でもすぐ来てもらえる
- 「かかりつけの病院名」「自宅住所」などを事前登録しておけるため、焦らず呼べる
- 破水やおしるしがあっても乗車可能なよう、車内が準備されている
- 到着後の対応がスムーズで、心強いサポートになる
赤ちゃん用品の準備

里帰り出産をしない場合、自宅に赤ちゃんを迎える準備を出産前にしっかり整えておくことが大切です。
産後すぐはママの体も回復途中で外出が難しくなりますし、赤ちゃんのお世話で時間もあっという間に過ぎてしまいます。
事前に用意しておくと安心なのは、次のようなアイテムです:
● すぐに使うベビー用品の例
- 肌着・ベビー服:短肌着・コンビ肌着・ツーウェイオールなど、洗い替え含めて5〜6枚ずつあると安心
- おむつ関連:新生児用おむつ、やわらかいおしりふき、布団や床を汚さないための防水シート
- 授乳グッズ:哺乳瓶や消毒セット、母乳パッド、授乳クッションなど(母乳・ミルクのどちらにも対応できるように)
- 寝具:赤ちゃん用布団、バスタオルやガーゼケットなどの代用も◎
- お風呂・衛生用品:ベビーバス、沐浴布、ベビーソープ、綿棒、つめ切りなど
● 購入のポイント
- 最低限からスタートし、必要に応じて買い足すスタイルがおすすめ
赤ちゃんの成長や生活スタイルに合わせて、「あったら便利」が変わってくるため、出産後にネット注文や家族の協力で買い足すのも◎ - ネット通販や宅配サービスを活用するのもひとつの手段
赤ちゃん用品専門店やAmazon・楽天などの「出産準備セット」も参考になります。
出産予定日をAmazonで登録すると、完全無料で様々な試供品の出産準備Boxがもらえるサービスもあり、オススメです!特に、オムツは試供品で様々なメーカーを試して、赤ちゃんに合うものをみつけるのがベスト。
→Amazonでもらえる〝出産準備お試しBoxをみてみる”
● 赤ちゃんの居場所づくりも忘れずに
赤ちゃんをお迎えする場所も整えておきましょう。
ベビーベッドを置くか、布団で一緒に寝るかなど、ご家庭のライフスタイルに合った環境づくりを考えておくと安心です。
たとえば:
- 日中の居場所(バウンサーやクーファンなど)
- 夜間の寝る場所(安全な睡眠スペースの確保)
- 授乳・おむつ替えがしやすいスペースの配置
焦らず、無理なく、赤ちゃんと過ごすイメージをふくらませながら準備を進めていくのが、不安も少しずつ和らげるポイントになります。
里帰り出産をしない場合の注意点

メリットだけでなく、気をつけたいポイントもあります。
育児や家事の負担が増える
退院後すぐにご自宅で赤ちゃんとの生活が始まります。
授乳やおむつ替えに追われながら、食事の準備や掃除・洗濯などの家事もこなすのは、想像以上に大変です。
特に、パパが仕事で不在がちだったり、サポートしてくれる人が少ない環境では、ママが育児も家事も一手に引き受けることになり、心身ともに疲れやすくなります。
だからこそ、出産前から役割分担や外部サービスの利用を考えておくことが大切です。
「すべてを完璧にやろう」と思わず、“頼れるところは頼る”という心構えで育児に臨むと、産後の生活がぐっと楽になります。
緊急時の対応策を確認する
赤ちゃんとの生活では、急な発熱や体調の変化、ママ自身の体調不良など、思いがけないことが起きることもあります。
里帰りをしない場合は、身近に頼れる人が少ない分、いざというときどう動くかを決めておくことがとても大切です。
事前に以下のようなことを確認しておくと安心です:
- 夜間・休日に受診できる小児科や産婦人科の場所と連絡先
- かかりつけの病院の救急対応の有無
- タクシーや自家用車での移動手段
- 近くに頼れる人がいない場合のサポートサービスや自治体の相談先
何かあったときに慌てず行動できるよう、メモを冷蔵庫など目に入る場所に貼っておくのもおすすめです。
「何かあったらどうしよう」と思うよりも、「何かあっても大丈夫」と思える準備があると、日々の育児にも余裕が生まれます。
体調管理に気をつける
出産後のママの体は、見た目以上にダメージを受けている状態です。
産後1カ月は「産褥期(さんじょくき)」と呼ばれ、子宮の回復やホルモンバランスの変化が進む、とても大切な時期。
里帰りをしない場合、サポートを受けられる人が限られるため、つい動きすぎてしまいがちですが、無理をすると回復が遅れたり、不調が長引くこともあります。
具体的には、次のような体調管理を意識しましょう:
- 十分な睡眠と休息をとる(赤ちゃんが寝ている間に一緒に休むのがおすすめ)
- 栄養バランスのとれた食事をとる(冷凍ストックや宅配弁当も活用)
- 悪露(おろ)の量や色に異変があれば、すぐに産院へ相談
- 発熱や強い疲労感、めまいなどがあれば無理せず受診を
「家のことをやらなきゃ」と思う気持ちは自然なことですが、まずはママが元気でいることが赤ちゃんにとって一番大切です。
「がんばりすぎない」くらいが、ちょうどいいです。
助産師の私からパパへお願い ママは赤ちゃんと寝てていいな♪と感じるかもしれませんが、それは違います。休んでいるように見えても、それは赤ちゃんのペース。もう少し寝ていたくても、起き上がるのが辛くても、赤ちゃんが起きたら、ママも頑張って起き上がってオムツを替え、授乳をしています。自分のペースで生活できない24時間この生活は想像以上に辛いものです。おうちのことは手抜きでOK!もしくはパパへ任せて!という大きな気持ちをお願いします。食事が冷凍食品でも、洗濯がたまっていてもOKですよね!優先すべきは、赤ちゃんのお世話とママの産後の回復です。
里帰り出産をしない場合に役立つサービス

最近では、外部の力を借りて快適に育児スタートを切る方も増えています。
産後ケア施設
産後ケア施設とは、赤ちゃんと一緒に滞在しながら、助産師や看護師のサポートを受けられる施設のことです。
出産後の体の回復を助けたり、育児の不安を相談したり、授乳や抱っこの仕方を教えてもらえる場所として利用される方が増えています。
里帰りをしない場合、家でひとりでがんばりすぎてしまうこともありますが、そんなときに産後ケア施設を利用すると、心身のリフレッシュや、育児に自信を持つきっかけになることも多いです。
施設によっては、1泊2日から利用できたり、日帰り(デイケア)対応のところもあります。
自治体の補助制度がある地域もあるので、住んでいる市区町村のホームページで事前に確認しておくのがおすすめです。
「少しでもゆっくり休みたい」「赤ちゃんのお世話に不安がある」というとき、頼れる場所があることは大きな安心につながります。
家事代行サービス
出産後は赤ちゃんのお世話で1日があっという間に過ぎてしまい、家事まで手が回らないことも多いです。
そんなときに頼りになるのが、掃除・洗濯・料理などを代わりに行ってくれる「家事代行サービス」です。
「人を家に呼ぶのはちょっと…」と感じる方もいらっしゃいますが、最近は産後のママ向けプランや、女性スタッフ限定の対応などもあり、安心して利用できるサービスが増えています。
たとえば…
- たまった洗濯や掃除をしてもらえる
- 栄養バランスのとれた作り置き料理を作ってもらえる
- 上の子の世話をしている間に、家のことをお願いできる
など、ママが「自分のために休む時間」をつくる手助けにもなります。
料金は1時間あたり数千円が目安ですが、自治体の補助や助成制度が使える地域もあるので、まずはお住まいの市区町村のサイトをチェックしてみるとよいでしょう。
「ちょっとだけ手を借りたい」というときに、無理せず利用できる選択肢があると心が軽くなります。
地域によりますが、家事サポートしてくれる事業者もあります。料理、掃除、買い物、ベビーシッターなど好きな家事を一定時間お願いできます。産後は、ママの体を休めることも大切。里帰りをしない場合は、一定期間だけでもサービスを利用する価値は大きいです。
家事代行サービス、してほしいことを依頼できるところをご案内します。東京が中心になります。
家事・育児の“助けて!”を丸っと解決。寄り添い型ご家庭サポート「きらりライフサポートベビーシッター
赤ちゃんのお世話はとても大切ですが、ママが一人で頑張りすぎると疲れてしまうことも。そんなときに頼りになるのが、ベビーシッターサービスです。
ベビーシッターは、専門の資格や研修を受けたスタッフが自宅に来て、赤ちゃんのお世話や簡単な家事を代わりに行ってくれます。
例えば、ママが休憩したい時や体調が優れない時、買い物や病院に行く間に見てもらえるので、とても心強い味方になります。
また、初めての育児で不安がある場合は、育児のアドバイスをしてくれるシッターさんも多く、育児のヒントやコツを教えてもらえることもあります。
料金は地域や時間帯によって異なりますが、1時間あたり数千円が一般的です。こちらも自治体によっては補助が出ることがあるので、事前に確認しておくと安心です。
「ちょっと手を借りたい」「気分転換したい」ときに、無理せず利用できるサービスとして知っておくと便利です。
保育士、看護師、経験者が中心となっているベビーシッターのベビーベルは全てLINEでのやり取りで完結し、採用時には犯罪歴や身元確認などもされているので安心して利用できます。
赤ちゃんのお風呂などもお願いできたり、病児ケアもあったりします。こちらも東京になりますが、どのようなサービスが受けられるのか参考にのぞいてみてはいかがでしょうか?
あなたと大切なお子さまを支えるベビーシッターサービス【ベビーベル】まとめ
里帰り出産をしない選択には、「慣れた環境で過ごせる」「夫がすぐ育児に参加できる」などのメリットがありますが、一方で生活リズムの変化や医療連携の難しさ、育児や家事の負担増などの注意点もあります。
そのため、家族や親せきのサポート体制を整えたり、陣痛タクシーの登録や赤ちゃん用品の準備をしっかり行うことが大切です。
また、急な体調不良や緊急時の対応策を事前に確認し、安心して過ごせる環境を作りましょう。
さらに、産後ケア施設や家事代行サービス、ベビーシッターといった外部サポートも上手に活用することで、ママの負担を減らし、心身ともに余裕をもって育児に取り組めます。
どんな選択でも、ママと赤ちゃんの健康と笑顔が一番。
無理せず、受けられるサポートは利用しながら、ママ自身の身体も大切にできる産後生活を送りましょう。

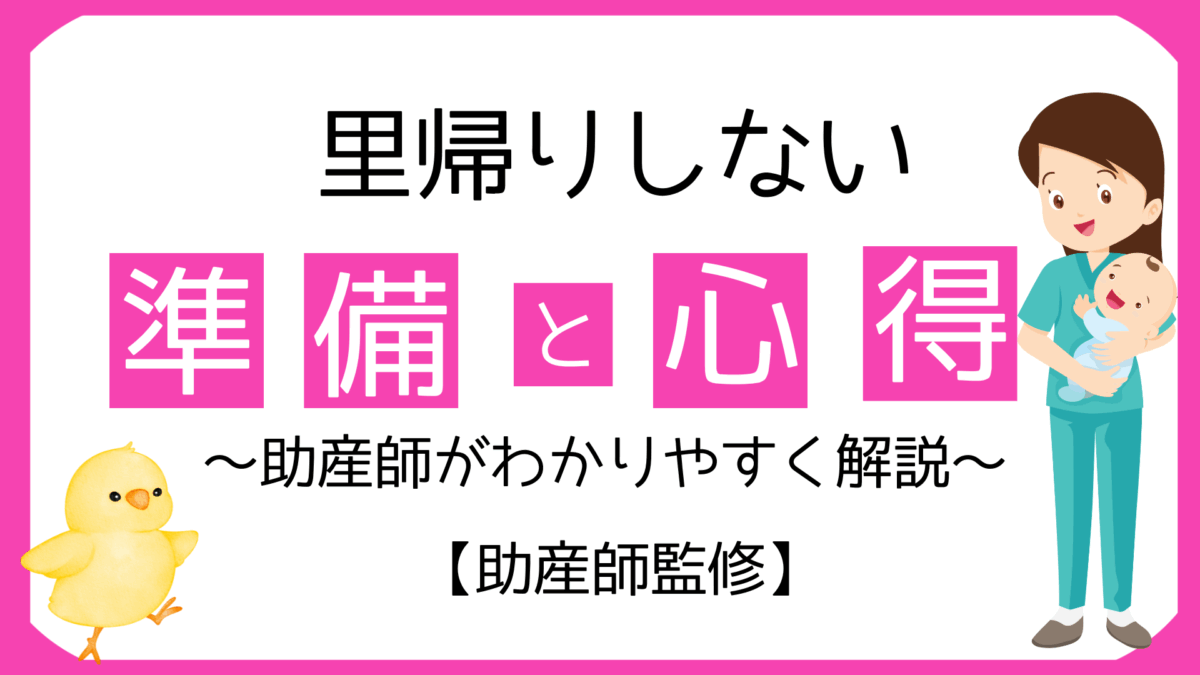
コメント