出産は人生の中でも大きなイベントであり、それに伴う費用も決して少なくありません。妊娠から出産、そしてその後の育児にかかる費用は、しっかりと計画を立てて準備することが大切です。
これを読めば、出産にかかる費用の基礎知識をはじめ、出産費用を軽減するための補助制度や保険、費用を抑えるためのポイントがわかるようになります。
出産に向けて、安心して準備できるように、役立つ情報をお届けします。
*当サイトは、プロモーションを含みます
出産費用の基礎知識

出産費用の平均額
日本での出産費用は、分娩方法や病院の種類、地域によって異なりますが、平均40万〜60万円程度とされています。
特に、都市部の私立病院や設備の整った産院では費用が高くなる傾向があり、個室の利用や無痛分娩を希望するとさらに費用が上がることがあります。無痛分娩の場合、追加費用として5万〜20万円程度かかるのが一般的です。
一方、公立病院や助産院では費用を抑え、自然分娩であれば出産育児一時金の範囲内で収まることも少なくありません。
出産費用に含まれるもの
出産費用には、以下のようなものが含まれます。
- 分娩・入院費用
- 新生児管理費
- 検査・処置費用
- 産後ケア・指導料
- 入院中の食事代
- その他の費用
詳細をみてみましょう!
1.分娩・入院費用
出産時に分娩には基本的な費用がかかりますが、下から産まれる自然分娩や、医療の力が必要になる吸引分娩、帝王切開によっても金額が異なります。また、入院費用には病室の利用料も含まれますが、個室を希望する場合は追加料金がかかります。
2.新生児管理費
赤ちゃんが生まれた後の健康チェックやケアに費用がかかります。保育器の利用が必要になった場合や、特別なケアが必要な場合は、かなり費用が発生することもありますが、保険適用になる場合もあります。
3.検査・処置費用
具体的には、血液検査や感染症検査、胎児の健康状態を確認するモニタリング検査などがあります。分娩時に、会陰(えいん)切開(膣の出口が狭い場合に切ってひろげる処置)や吸引分娩、縫合処置、点滴、麻酔(無痛分娩や帝王切開の場合)などの処置費用が発生することもあります。
4.産後ケア・指導料
出産後の母体の回復をサポートするためのケア費用や、授乳・育児指導の費用が含まれます。 病院や産院によっては、助産師による母乳マッサージや育児相談、退院後のフォローアップが提供されます。
5.入院中の食事代
入院中に提供される食事の費用です。一般的には1日3食が提供され、産院によっては栄養バランスを考えた特別メニューや、お祝い膳(出産後に提供される特別な食事)が含まれます。
6.その他の費用
出産費用には基本的な分娩・入院費用が含まれますが、病院や産院のサービスによっては、以下のような費用が別途かかる場合があります。
- 特別室・個室料金:大部屋の場合は、部屋料金はかからないことも多いですが、個室などは確認しておきましょう。部屋の広さや設備(電子レンジやミニキッチン、家族用ベッドの有無など)によって変わります。
- 無痛分娩費用:無痛分娩を選択する場合、追加で5万〜20万円程度の費用がかかるのが一般的です。麻酔薬の使用量や回数、夜間・休日などの日時加算など、産院により設定されています。2025年3月現在、健康保険の適用外(自由診療)となるため、自己負担となります。
- 添い寝付きの宿泊費:家族が宿泊できる部屋や宿泊時のみ布団を借りたりする場合、布団代などが必要となることも。
- アメニティ・記念品:産院によっては、出産記念の品など準備してくれている場合もあります。
- お祝い膳:産院により、入院中にお祝い膳が提供されることがあります。
これらの追加費用は病院や産院によって大きく異なるため、事前に確認し、希望するサービスに合わせて準備をしておくことが大切です。
出産費用に影響を与える要因

施設の種類
出産費用は、どのような施設で出産するかによって大きく違ってきます。大きく分けて次の3種類。
- ジェネリック(公立・私立)
- 産婦人科クリニック(個人病院)
- 助産院
詳細をみてみましょう!
1. ジェネリック(公立・私立)
ジェネリック施設は、費用を抑えながら安心して出産したい人におすすめの選択肢です。
特徴
産婦人科以外にも小児科やNICU(新生児集中治療室)などの設備が整っており、ハイリスク出産にも対応が可能。
公立病院の場合、医療費が比較的安く抑えらる傾向があります。
個室を希望していても、希望通りにできないこともあり、大部屋になってしまうこともあります。
費用の目安
- 公立病院(市立・県立・国立病院など):約40万~50万円
- 大学病院:約50万~70万円
2. 産婦人科クリニック(個人病院)
快適な環境で手厚いケアを受けたい人や、無分娩を希望する人におすすめの選択肢です。
特徴
・快適な環境と手厚いサービス 個室が充実しているため、プライバシーが確保されます。
アメニティやお祝い膳、エステなど、ホテルのようなサービスを提供する産院が多くあります。
産後のケアや授乳指導、母乳相談などが充実しています。
・痛みのない分娩の選択肢が多い 無痛分娩(硬膜外麻酔)を導入している施設が多く、計画的、選択的に無痛分娩を行っている産院もみられます。
麻酔医が麻酔の管理をしてくれる産院も多くあります。
・医師や助産師との距離が近い 院長が妊娠中から入院中など、要所を押さえる産院も多く、院長以外に医師がいる場合も大きな病院よりは距離が近くなります。
助産師も外来から入院中、退院後まで継続的にアドバイスしてくれることも多いです。
アットホームな雰囲気の産院も多くあります。
費用の目安
- 50万〜100万円以上:無痛分娩を利用したり、吸引分娩、帝王切開など様々な処置によっても変わります。個室費用なども様々です。緊急時の処置など出産してみないと分からない部分もありますが、料金は事前に確認しましょう。
- 高級産院の場合:サービスが充実しており、すべて個室、アメニティが充実、エステも実施、退院前にご夫婦でお祝い膳を食べることができるなど、産院によって様々なサービスがあります。産院によって、サービス内容、費用は異なりますので、何を希望するか、費用面はどうかなど確認しましょう。
注意点
- 費用が高い:公立病院に比べ、個人病院は費用が高くなる傾向にあります。
- 緊急時に対応に限りがある:産科のみで、小児科がない、NICU(新生児集中治療室)がないなどの理由から、出生したベビーが産科で対応できないレベルの場合、NICUなどのある病院へ赤ちゃんのみ救急搬送されることもあります。
- 人気の病院は予約が早く埋まる:分娩予定日が決まる妊娠8週あたりで産院に連絡しても予約がいっぱいで断られることもあります。人気の産院の場合は、赤ちゃんの心拍が見える妊娠6週あたりで予約いれましょう。
3. 助産院
合併症がない健康な方で、妊娠中も自己管理(太りすぎないなど)など意識しておこなえる方、アットホームな雰囲気で出産をしたい方に向いています。
特徴
・助産師が運営しています。
・医師がいないため、異常時に引き受けてくれる提携病院が必ずあります。
・妊娠中、数回は提携病院での医師による診察が必要です。
・通常分娩(リスクの低い自然分娩)のみ対応し、医療介入は極力抑えられます。
・自然なお産を希望する人向けで、アットホームな雰囲気でリラックスしやすくなります。
・出産時は、家族に囲まれて赤ちゃんを迎えることもできます。
・医療設備がなく、医師はいないため、妊娠中や出産時、万が一の異常時には医療機関への搬送が必要になります。
費用の目安
約35万~60万円が一般的です。助産院での出産も「出産育児一時金(50万円)」の対象となります。
注意点
- 正常分娩のみの対応になる:帝王切開や医療的な処置が必要な場合は対応不可。
- 緊急時に対応に限りがある:緊急時は提携病院への搬送が必要です。出生した赤ちゃんの異常時は、赤ちゃんのみ搬送されることもあります。
- 麻酔・医療処置はなし:無痛分娩や陣痛促進剤の使用はできません。
- 設備・サービスの違いを確認:病院などとは設備やサービスも大きく異なるため、確認しておきましょう。
- 健康保険適用外の部分がある:「出産育児一時金(50万円)」の対象にはなるが、医療行為を伴わないため健康保険の適用外となる部分があります。例えば、産後ケア、入院中の追加サービスなどは自己負担になる場合があるので、事前に費用の詳細を確認しておくと安心です。
- 家族の立ち会いや宿泊の可否を確認:夫や上の子も出産に立ち合いが可能で、宿泊も可能な場合が多いですが、確認しておきましょう。
施設選びのポイント
出産費用を抑えたい場合は、公立の総合病院や助産院を選ぶと比較的安くなります。一方、快適な環境や手厚いサポートを求める場合は、産婦人科クリニックが適している場合があります。
地域差
出産費用は、住んでいる地域によって大きく異なります。 特に都市部と地方では、医療機関の運営コストや物価の違いが影響し、費用の相場に差が出ることが一般的です。
1. 都市部は費用が高い
東京都や大阪府などの大都市圏では、土地代や人件費が高いことに加え、病院の設備やサービスが充実しているためです。特に、個室の利用や無痛分娩を希望する場合には、金額がさらに高くなることがあります。
2. 地方は比較的安価
地方の病院や助産院では、都市部に比較して分娩費用の平均額が全国平均より低い地域もあり、出産一時金(50万円)内でほぼ賄えるケースもあります。
出産を希望する方法(無痛分娩や特別なケアなど)を希望しても、施設自体が導入しておらず実現しにくい場合もありますので、事前の確認が重要です。
3. 自治体ごとの補助金の違い
自治体ごと出産育児一時金(50万円)に独自の上乗せを行っている自治体もあれば、補助回数が多い自治体もあります。
ご自身の自治体の支援制度は、住んでいる地域によって大きく異なるため、事前に自治体の公式サイトなどで確認しておくと、出産費用の負担を軽減できる可能性があります。
出産費用を抑えたい場合は、地域ごとの相場や補助制度を調べたうえで、施設を考えるとよいでしょう。
分娩方法
医療介入の少ない自然分娩が最も費用を抑えられ、無痛分娩や帝王切開になると医療介入しているため、出産費用は高額になります。
1. 自然分娩(経腟分娩)
通常の経腟40万~60万円程度が目安になります。
2. 無痛分娩
麻酔を使用するため、医療的な管理も多く必要になり、自然分娩の費用に加えて10万~20万円程度の追加費用をみておきましょう(目安です)。
3. 帝王切開術
手術が自然分娩よりも費用が高くなり、60万~100万円程度となることが多いです。高額療養費制度を利用することで自己負担額を抑えられる可能性があります。手術なので、ご自身で生命保険加入などされている場合は対象になることもありため、確認しましょう。
出産に関するその他の費用
妊婦健診の費用
一般的に健診は、14回前後の受診が推奨されています。 1回の費用は3,000円〜10,000円程度ですが、健診内容によって異なります。
主な内容と費用の目安
| 健診内容 | 費用の目安 |
|---|---|
| まずは(妊娠確定診断) | 5,000円〜10,000円 |
| 超音波検査 | 3,000円〜5,000円 |
| 血液検査 | 5,000円〜10,000円 |
| 子宮頸がん検査 | 2,000円〜5,000円 |
| 妊娠後の血液検査 | 5,000円〜10,000円 |
合計すると自己負担額は約10万〜15万円になることもあります。
費用を軽減する方法
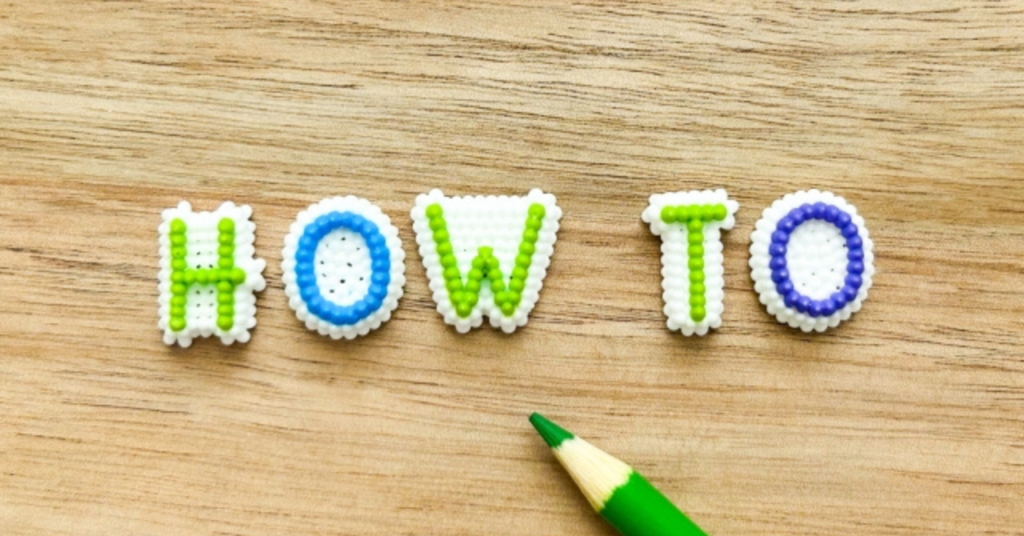
①補助券を活用する
自治体から交付される「補助券(受診券)」を使えば、健診費用の一部をカバーできます。補助の内容は自治体ごとに異なりますが、多くの場合、14回分の健診費用が助成されます。
💡ポイント
- 妊娠届を提出すると母子手帳と一緒に補助券がもらえます。
- 補助券が使える医療機関を事前に確認しましょう。
② 医療費免除を申請する
支払った費用は医療費免除の対象になるため、年間10万円を超えるの医療費を支払った場合、確定申告で一部が還付される可能性があります。
💡ポイント
- 交通費(タクシー代など)も一部対象になります。
- 領収書をしっかり保管しておきましょう。
- 出産に関わる費用だけでなく、歯科医院など受診した病院の領収証や薬局で購入した薬の領収証も含まれる場合があるので保管しておきましょう。
③追加検査の費用を確認する
妊娠経過によっては、糖負荷試験や羊水検査などの追加検査が必要になることもあります。
妊娠がわかったら、まずは自治体の助成内容を確認し、上手に活用していきましょう!
マタニティ用品の費用
妊娠がわかると、体型の変化や体調の変動に合わせて、マタニティ用品を揃える必要が出てきます。
妊娠中に必要なママ自身のマタニティ用品をみていきましょう。
備品の費用の目安

マタニティ用品にかかる費用総額は、3万円〜10万円程度が一般的です。
1.マタニティウェア(合計1万〜5万円)
妊娠中期〜後期にかけてお腹が大きくなりますが、普段の服では締めつけがきつくなり、動きにくくなることがあります。
| アイテム | 特徴 | 費用目安 |
|---|---|---|
| マタニティパンツ・スカート | ウエストが伸縮するもので、腹部をサポートするタイプが快適 | 3,000〜15,000円 |
| マタニティトップス | お腹が大きくなっても快適に着られるよう、ゆったりとしたデザインのものを選ぶのがベスト | 2,000~8,000円 |
| インナーウェア | マタニティ用のブラジャーやショーツで、おなかや胸をサポートして腰などへの負担を軽減 | 1,500~8,000円 |
| マタニティパジャマ | 出産後の授乳まで考慮したデザインのものを揃えておくと便利 | 3,000~10,000円 |
💡節約のポイント
✔ウエストが調節できるスカートやワンピースで代用できるものは代用してOK!
✔ フリマアプリやレンタルサービス、季節ごとのセールやアウトレットを上手に活用するのもオススメ。
2.マタニティインナー(合計5,000円〜2万円)
妊娠するとバストが大きくなり、普通の下着では締めつけがきつくなることもあるので、きつくないけれどサポート感のあるものを選びましょう。
| アイテム | 費用目安 |
|---|---|
| マタニティブラジャー | 1,500~5,000円 |
| マタニティショーツ | 800~2,500円 |
| 授乳キャミソール | 1,500~3,500円 |
| 産後リフォームインナー【妊娠中も可】 (骨盤ベルト・ウエストニッパー) | 3,000~10,000円 |
💡節約のポイント
✔セット購入: マタニティインナーはセットで購入することで、単品よりも割引があるものを選ぶ!
✔多機能アイテムの選択: 授乳用としても使えるマタニティブラやインナーを選ぶことで、出産後も長く使えるため、コストパフォーマンスがUP!
3. 妊娠中のケア用品(合計3,000円〜1万円)
妊娠すると、肌の乾燥やむくみ、腰痛など体の変化が起こります
。
| アイテム | 費用目安 |
|---|---|
| 妊娠線予防クリーム・オイル | 1,500〜5,000円 |
| 着圧ソックス | 1,000〜3,000円 |
| 骨盤ベルト | 3,000~10,000円 |
| 抱き枕(授乳クッション兼用) | 3,000~7,000円 |
| ノンカフェイン飲料(ルイボスティー、たんぽぽ珈琲など) | 500~2,000円 |
💡節約のポイント
✔ 妊娠線予防は手持ちの保湿アイテムで代用:高価な専用クリームでなく、ニベアやワセリン、ホホバオイルなどで代用可能
✔ 骨盤ベルトは出産後も使えるものを選ぶ:産前産後兼用のタイプなら長く使える
マタニティ用品の費用を節約するコツ
1. フリマアプリやレンタルを活用
メルカリやラクマなどのフリマアプリを利用すれば、未使用品や美品を安く手に入れることができます。特に、妊娠中しか使わない骨盤ベルトやマタニティウェアは、お下がりや中古でも十分使えます。また、マタニティフォーマルや抱き枕など、一時的にしか必要ないものはレンタルサービスを活用するのもおすすめです。
2. 産後も使えるデザインを選ぶ
マタニティウェアやインナーは、授乳対応のものやシンプルなデザインのものを選ぶと、産後も長く使えて無駄がありません。特に、授乳キャミソールや前開きのパジャマは、産後の授乳期にも活躍します。
3. 必要最低限の枚数を揃える
妊娠期間は限られているため、マタニティ服やインナーを買いすぎないことが大切です。洗い替えを考慮しつつ、最低限の枚数でやりくりすれば出費を抑えられます。特に、部屋着は手持ちの大きめサイズの服で代用できることもあります。
4. 普段使いのアイテムで代用する
専用品を買わずに、普段使っているもので代用できることもあります。例えば、妊娠線予防クリームはニベアやワセリン、ホホバオイルなどでもOK。着圧ソックスも、市販のものの中からゆるめのタイプを選べば問題ありません。
5. プチプラブランドやアウトレットを活用
西松屋、ユニクロ、無印良品、H&Mなどのプチプラブランドなら、マタニティ服やインナーをリーズナブルに揃えられます。また、アウトレットやセール時期を狙えば、さらにお得に購入可能です。
6. 友人や家族からお下がりをもらう
短期間しか使わないマタニティウェアやグッズは、先輩ママから譲ってもらうのも良い方法です。特に、妊娠中だけ使う骨盤ベルトや抱き枕などは、お下がりで十分役立ちます。
7. クーポンやポイントを活用する
楽天市場やAmazon、赤ちゃん本舗などのオンラインショップでは、クーポンやポイント還元があることが多いです。特に、楽天お買い物マラソンやセール期間を狙うと、よりお得に購入できます。
これらの方法を組み合わせることで、マタニティ用品の費用をグッと抑えられます!
マタニティ用品の費用を抑えて快適な妊娠生活を!
マタニティ用品は妊娠期間中だけのものが多いため、賢く選んで無駄な出費を抑えることが大切です。フリマアプリやレンタルを活用したり、産後も使えるアイテムを選んだりすることで、コストを抑えながら必要なものを揃えられます。また、プチプラブランドやお下がりを活用すれば、品質の良いアイテムをお得に手に入れることも可能です。
一方で、妊娠線予防や骨盤サポートなど、体のケアに関わるものはできるだけ自分に合ったものを選び、快適な妊娠生活を送ることも大切です。上手に節約しながら、自分の体調やライフスタイルに合ったマタニティ用品を取り入れて、楽しく快適なマタニティライフを過ごしましょう!
出産の費用だけでなく、妊娠中に産後に必要となる手続き準備も考えておきましょう。こちら「産後の手続き」から参考に準備しておきましょう。

出産費用を補助する制度

日本には出産にかかる費用を軽減するためのさまざまな補助制度が整っています。これらの制度を上手に活用することで、経済的な負担を大幅に軽減することが可能です。ここでは、出産育児一時金や高額療養費制度、医療費控除、出産手当金、出産費貸付制度など、主な補助制度についてご紹介します。
出産育児一時金
出産育児一時金は、出産にかかる費用をサポートするために健康保険から支給される制度です。2023年4月から支給額が引き上げられ、現在は1児につき50万円(産科医療補償制度の対象外の場合は48.8万円)支給されます。
対象者
- 健康保険に加入している本人、または扶養されている配偶者
- 妊娠85日(4ヶ月)以上の出産(早産・流産・死産も含む)
申請方法と受け取り方
① 直接支払制度(推奨)
出産費用として医療機関に直接支払われる制度。自己負担を減らせるため、多くの人が利用しています。
② 受取代理制度
医療機関が申請を代行し、出産後に医療機関へ支払われる方法。
③ 事後申請
出産費用を一旦自己負担し、後で健康保険に申請して支給を受ける方法。
ポイント・注意点
- 出産費用が50万円未満の場合は、差額が本人に支給されます。
- 海外での出産でも一定の条件を満たせば申請可能。
- 国民健康保険・社会保険どちらでも利用可能だが、勤務先の健康保険組合によって独自の付加給付がある場合も。
出産にかかる経済的負担を軽減できる重要な制度なので、事前に確認し、スムーズに利用できるよう準備しましょう。
妊婦健診の費用助成
妊婦健診の費用助成は、妊娠中の定期健診にかかる費用を自治体が補助する制度です。妊婦健診は健康保険の適用外ですが、母子の健康を守るために多くの自治体で助成制度が設けられています。
助成内容
- 助成回数:基本的に 14回分(自治体によって異なる)
- 助成金額:1回あたり 4,000円〜10,000円程度(検査内容による)
- 対象の健診:血液検査、尿検査、超音波検査、子宮頸がん検診など
助成の受け方
① 母子健康手帳の交付時に「妊婦健診補助券(受診票)」を受け取る
② 健診時に補助券を提出し、助成額を差し引いた分を自己負担
③ 補助券の範囲を超えた費用は自己負担(追加の超音波検査など)
ポイント・注意点
- 自治体によって助成金額や回数が異なるため、住んでいる地域の制度を確認することが大切。
- 助成券が使える医療機関が決まっているので、事前に確認を!
- 里帰り出産の場合、一旦自己負担して後日自治体に申請すると助成を受けられることが多い。
妊婦健診は赤ちゃんとお母さんの健康を守るために欠かせないもの。助成制度をしっかり活用して、安心して妊娠生活を送りましょう!
高額療養費制度
高額療養費制度は、1ヶ月の医療費が一定額を超えた場合に、超過分を払い戻してもらえる制度です。出産は通常「正常分娩」の場合は健康保険の適用外ですが、帝王切開・吸引分娩・鉗子分娩・妊娠高血圧症候群・早産・切迫早産など、医療行為が伴う出産は健康保険の対象となり、この制度を利用できます。
自己負担限度額(例)
限度額は年収や健康保険の種類によって異なりますが、例えば以下のように決まっています。(70歳未満の場合)
| 年収(目安) | 自己負担限度額(月) |
|---|---|
| 約1,160万円~ | 約252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
| 約770万~1,160万円 | 約167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
| 約370万~770万円 | 約80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
| 約370万円以下 | 約57,600円 |
| 住民税非課税世帯 | 約35,400円 |
※同じ医療機関で同月内にかかった医療費が対象。
申請方法
① 事前申請(おすすめ):「限度額適用認定証」を取得し、病院窓口で提示すれば、窓口での支払いが限度額までになる。
② 事後申請:いったん全額を支払い、後日健康保険に申請して払い戻しを受ける。
ポイント・注意点
- 出産育児一時金とは別で適用可能なので、帝王切開などの場合は両方利用できる。
- 世帯合算が可能:家族の医療費と合算して限度額を超えた場合も申請できる。
- 過去2年以内の支払いでも申請可能:申請し忘れた場合でも、2年以内なら払い戻し可能。
帝王切開や医療的ケアが必要な出産では医療費が高額になりがちですが、この制度を活用することで大幅に負担を軽減できます。事前に「限度額適用認定証」を取得しておくと、支払い時の負担が減るので安心です!
医療費控除
医療費控除は、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が10万円(または所得の5%)を超えた場合に、確定申告をすることで所得税の一部が還付される制度です。出産にかかる費用の一部も対象となるため、帝王切開や妊婦健診、自費診療分などを含めると控除を受けられる可能性があります。
対象となる医療費の例
✅ 出産に関するもの
- 帝王切開・吸引分娩・鉗子分娩などの医療費
- 妊婦健診の自己負担分
- 入院費(個室代は対象外の場合あり)
- 出産時の交通費(タクシー代など)
- 助産院での分娩費用
- 不妊治療費
✅ 家族の医療費も合算可能
- 配偶者や子どもの医療費も合算できる
- 世帯で10万円を超えていれば申請OK
控除額の計算方法
(支払った医療費 - 保険などで補填された額 - 10万円 or 所得の5%) = 控除対象額
たとえば、
- 妊娠・出産にかかった医療費が 50万円
- 出産育児一時金で 50万円補填
この場合、控除額は 0円 になり対象外
しかし、
- 医療費 60万円
- 出産育児一時金 50万円
- 自己負担額 10万円 → 控除対象
申請方法
① 医療費の領収書を保管(オンライン確定申告なら明細書の記入のみでOK)
② 確定申告をする(2月16日~3月15日)
③ 税金の還付を受ける(所得税が軽減される)
ポイント・注意点
- 出産育児一時金や高額療養費制度で補填された分は差し引く
- 通院時のタクシー代も対象(公共交通機関が使えない場合)
- 5年間さかのぼって申請可能
出産費用は高額になりがちなので、医療費控除を活用すれば負担を軽減できます。妊娠が分かったら領収書を保管しておき、確定申告の準備をしておくと安心です!
出産手当金
出産手当金は、会社員や公務員など健康保険に加入している人が、産休中に給与の代わりとして受け取れる給付金です。出産による収入減を補うための制度で、産前産後の休業期間中に支給されます。
支給対象者
✅ 会社員・公務員など健康保険(社会保険)に加入している人
✅ 産休(産前42日・産後56日)を取得している人
✅ 産休中に給与が支払われていない、または給与が減額されている人
※ 国民健康保険加入者(自営業・専業主婦など)は対象外
支給期間
- 産前42日(多胎妊娠の場合は98日)+ 産後56日 = 計98日間
- 出産が予定日より遅れた場合、その分も延長される
支給額の計算方法
1日あたりの支給額 = 休業開始前の直近12ヶ月間の標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3
✅ 計算例(標準報酬月額30万円の場合)
30万円 ÷ 30 × 2/3 = 6,667円/日
→ 98日間休業の場合、約65万円支給
申請方法
① 勤務先に産休を申請
② 健康保険(協会けんぽ or 健保組合)へ申請書類を提出(産後に申請)
③ 審査後、出産手当金が振り込まれる
ポイント・注意点
- 退職後でも受給可能(退職日までに産休に入っていればOK)
- 出産予定日より早く産まれた場合も42日間分は支給される
- 産休中に給与が支払われている場合は、その分差し引かれる
出産後の生活費をサポートしてくれる大切な制度なので、条件に当てはまる場合は忘れずに申請しましょう!
出産費貸付制度
出産費貸付制度は、出産育児一時金の支給前に、出産費用の一部または全額を無利子で借りられる制度です。出産前後は何かと出費がかさむため、一時的に資金が必要な場合に活用できます。
対象者
✅ 健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険)に加入している人
✅ 出産育児一時金を受け取る予定の人
貸付額
- 最大50万円(出産育児一時金の範囲内)
- 申請時に希望額を選択できる
申請方法
① 健康保険の窓口または勤務先に申請書を提出
② 審査後、指定の口座へ貸付金が振り込まれる
③ 出産後、出産育児一時金が支給される際に貸付金が相殺される(不足分があれば追加支給、余った場合は返金が必要)
ポイント・注意点
- 無利子で借りられるため、金銭的な負担が増えない
- 病院の「直接支払制度」を利用する場合は不要なことが多い
- 出産育児一時金の範囲内での貸付なので、原則として返済義務なし
出産前にまとまった費用が必要な場合、安心して利用できる制度です。資金に不安がある方は、早めに勤務先や保険窓口で確認しておくとよいでしょう!
出産費用に備える保険の選び方

出産には予想以上の費用がかかることもあります。事前に計画的に準備をすることで、経済的な負担を軽減できます。特に、医療保険や学資保険などの保険は、出産時の費用やその後の子どもの教育費用に備えるための重要な手段です。ここでは、出産に備えるために選ぶべき保険のポイントを、医療保険と学資保険の2つに分けてご紹介します。
医療保険
医療保険は、病気やケガによる入院や手術にかかる費用をカバーする保険です。出産に関しても、帝王切開や合併症による治療費などがカバーされる場合があり、出産費用に備える一環として検討する価値があります。
医療保険がカバーする出産費用
医療保険は、正常分娩を対象としていない場合が多いですが、以下のようなケースではカバーされることがあります。
- 帝王切開
帝王切開が必要になった場合の手術費や入院費 - 妊娠高血圧症候群
妊娠中に発症した病気による治療費や入院費 - 早産・切迫早産
予定より早く生まれた場合の入院費用 - 合併症による治療
妊娠中または出産時に発生した合併症に関連する治療費用
医療保険の選び方
- 出産後も保険が適用されるプランを選ぶ
妊娠中の医療費に関しては、妊娠中に加入した医療保険が適用されることは少ないため、妊娠前に加入しておくことが重要です。選ぶ際には、産後も継続して保険が適用されるタイプの医療保険を選びましょう。 - 保障内容をチェック
保険によっては、出産に関する治療費を一部または全額カバーしてくれるものもあります。特に、帝王切開や早産、妊娠高血圧症候群などに備える保障があるかどうか確認しましょう。 - 入院日額の金額を確認
入院日額が高ければ、高額な入院費用も負担を軽減できます。出産時に予期せぬ長期入院が必要になる場合もあるため、日額の補償額が適切かどうかをチェックしてください。 - 特約を活用する
**「出産一時金特約」や「入院特約」**を付帯できる保険もあり、こうした特約を活用すると、出産時の支出に対する補償が充実します。特に高額な帝王切開や入院を予定している場合、追加の保障を加えることで安心感が増します。
医療保険加入のタイミング
医療保険に加入するタイミングは、妊娠前に加入しておくのが理想です。妊娠中に加入しようとしても、妊娠が分かってからでは加入が難しくなることが多いため、計画的に準備しておきましょう。また、既に妊娠している場合でも、出産後の入院費や治療費を補償するために、出産後に加入しても補償を受けることができます。
ポイント・注意点
- 保険内容や保障期間をしっかり確認すること
- 出産一時金と医療保険の補償が重なる部分を確認して、重複しないように調整
- 保険料と保障内容のバランスをよく考えることが大切
出産に備えるための医療保険選びでは、保障内容の詳細を理解し、妊娠前からの準備が鍵になります。出産後の経済的負担を軽減するためにも、自分に合ったプランを選びましょう!
学資保険
学資保険は、子どもの教育費用に備えるための保険です。通常、子どもが成長するにつれてかかる教育費(学費)を計画的に積み立てることができるため、出産後の準備として早めに加入しておくことが推奨されます。学資保険は、子どもの進学時期に合わせて給付金を受け取ることができるため、学費の負担を軽減するのに役立ちます。
学資保険の特徴
- 子どもの進学に合わせた支給タイミング
- 学資保険では、子どもが小学校入学時、大学入学時など、進学時期に合わせて一時金や月々の給付金を受け取ることができます。
- 保険料の支払い方法
- 月払いや年払いで支払い、将来必要な学費に備える。支払期間や支払い額を自由に設定することができるプランもあります。
- 満期保険金
- 子どもが成人するタイミングで満期保険金を受け取ることができ、その金額を大学進学やその後の生活費用に充てることができます。
- 保障内容
- 死亡保障や高度障害保障がついているものもあり、万が一の事故や病気で親が働けなくなった場合でも、支払いが続き、子どもの教育費が確保されます。
学資保険の種類
- 終身保険タイプ
- 保険期間が一生涯続き、満期時には積立金に加え、死亡保障もついてくる。
- 定期保険タイプ
- 支払い期間が一定期間(例えば20年など)で終了し、その後は支払いがありません。積立てた金額が満期時に支払われます。
- 返戻金型
- 支払った保険料が、途中で支払った分以上に戻ってくるタイプ。いわゆる「返戻金」が多いプランです。
学資保険加入のタイミング
- 出産前後が最適
学資保険は、早ければ早いほど月々の保険料が安く済みます。また、加入時期が早いほど、積立金が時間をかけて増えるので、教育費用の準備に余裕を持つことができます。 - 子どもが生まれたらすぐに加入することで、子どもの成長とともに必要な資金を計画的に準備できます。
学資保険選びのポイント
- 保障内容を確認
学資保険の主な目的は、教育資金の積立ですが、万が一の保障がついているか、または特約で追加できるかどうかも確認しておきましょう。 - 返戻率(戻り金)をチェック
返戻率が高い商品ほど、積立金が効率的に増えるため、学資保険選びでは返戻率をチェックしておくとよいです。ただし、返戻率だけにこだわらず、全体の保障内容とのバランスも大切です。 - 積立金の額を考える
進学時に必要な学費の金額を想定し、計画的に積立額を決定します。大学進学時にかかる費用や、私立学校、海外留学などのシナリオも考慮して選びましょう。
ポイント・注意点
- 学資保険は長期間続ける保険なので、途中で解約すると元本割れすることもあります。継続的に支払える額を設定することが大切です。
- 途中で支払いが困難になった場合、払込免除特約をつけることで、一定条件を満たすと支払いが免除されるケースもあります。
出産後、子どもが成長するにつれて教育費用の準備は大きな課題になります。早期に学資保険を活用することで、教育資金を効率的に準備でき、将来の学費の負担を軽減することができます。
早めの加入がおすすめされる学資保険、どんなものか、費用負担がどれくらいなのか、入っていれば何が安心なのか…など様々な不安があって当然なので、何も分からない状態でOK!とりあえず、プロに相談してみましょう。
ご紹介させていただくのは、保険会社や代理店ではなく、たくさんの保険プランの中から、どこの保険がぴったりかを一緒に考えて紹介してくれるサイトです。保険だけではなく、看護師の無料健康相談サービス付きです。下記サイトをご参照ください。
妊娠〜出産〜子育て中の「ママ」のための保険無料相談サービス【ベビープラネット】【筆者が入った保険】出産後、学資保険に入りました。医療費は、一部負担だったり、無料だったりだったので負担は少ないと考え、お金がかかるであろう高校入学時と大学進学時、大学3回生にあがる時の3回に費用が下りる学資保険でした。入学金や授業料に加え、制服代や教科書など一度にお金が必要になるときに、保険金がおりてきたので契約して正解だったと思います!とっても助かりました。医療保険には加入しませんでしたが、学資保険は「親が死亡時には保険料は払う必要がなくなるけれど、子どもには契約通りの金額が下りるもの」でした。
出産費用に関するよくある質問

海外での出産で使える補助制度は?
海外で出産する場合でも一定の補助制度が利用できることがありますが、具体的な内容は、居住地や加入している健康保険によって異なるため、事前に確認が必要です。
出産育児一時金: 日本の健康保険に加入している場合、妊娠週数22週以降出産すると出産育児一時金が支給されます。海外で出産した場合でも、申請を行うことで受け取ることができます。金額は健康保険によって異なりますが、一般的には一児につき50万円(2023年以降)です。
海外療養費制度: 海外での医療費が発生した場合、海外療養費制度を利用することで、一定の条件を満たせば医療費の一部が払い戻されることがあります。出産にかかる医療費も対象となる場合がありますので、事前に確認が必要です。
健康保険の適用: 一部の健康保険では、海外での出産に対しても保険適用がある場合があります。具体的な適用条件や手続きについては、加入している健康保険の窓口で確認してください。
帰国後の手続き: 海外で出産した場合、帰国後に必要な手続きを行うことで、出産育児一時金や海外療養費の申請が可能です。出産証明書や医療費の領収書など、必要な書類を準備しておくことが重要です。
注意点
- 海外での出産に関する補助制度は、国や地域によって異なるため、事前に情報を収集し、必要な手続きを確認しておくことが大切です。
- 出産に関する補助制度の詳細や手続きについては、必ず、加入している健康保険の窓口や公式サイトで確認しましょう。
出産費用に関する保険適用の条件は?
出産にかかる費用は、健康保険の適用を受けることができますが、以下の条件を満たす必要があります。
加入している健康保険: 出産費用の保険適用を受けるためには、被保険者が健康保険に加入していることが前提です。国民健康保険や社会保険など、各種健康保険制度に基づいて適用されます。
出産の種類: 自然分娩や帝王切開など、出産の種類によって保険適用の範囲が異なる場合があります。一般的には、医療機関での出産が対象となります。
医療機関の指定: 保険適用を受けるためには、出産を行う医療機関が健康保険の契約医療機関である必要があります。事前に産院に確認しておくことが重要です。
出産育児一時金の申請: 出産にかかる費用の一部は、出産育児一時金として支給されます。この金額は、健康保険によって異なりますが、申請を行うことで受け取ることができます。
必要書類の提出: 保険適用を受けるためには、出産証明書や健康保険証など、必要な書類を医療機関や保険者に提出する必要があります。
- これらの条件を満たすことで、出産にかかる費用の一部が健康保険から支給されるため、事前に加入している健康保険の窓口や公式サイトで確認し、必要な手続きを行うようにしましょう。
まとめ:出産準備と賢い選択で安心な出産生活を!
出産は人生の大きなイベントであり、その費用も重要な準備の一つです。出産費用の平均額は施設や分娩方法、地域によって異なりますが、費用の大部分を占めるのは入院費や手術費です。施設の種類(公立・私立)、分娩方法(自然分娩・帝王切開)、追加サービス(個室代や食事代)などが費用に大きく影響します。また、出産に伴ってかかる費用には、妊婦健診や出産後のケア、育児用品なども含まれるため、全体的な費用をしっかり見積もることが大切です。
費用を軽減する方法としては、公的補助制度(出産育児一時金、妊婦健診の助成、高額療養費制度など)の活用や、医療保険、学資保険を通じて長期的な支援を受けることが挙げられます。また、施設選びも費用に大きな影響を与えるため、自分たちのニーズに合った施設を選ぶことが重要です。
しっかりと準備し、必要な補助や制度をうまく活用すれば、出産費用の負担を軽減でき、安心して出産に臨むことができます。出産に向けての準備を早めに行い、適切な支援を受けることで、経済的にも精神的にも安心できる出産生活を送りましょう!

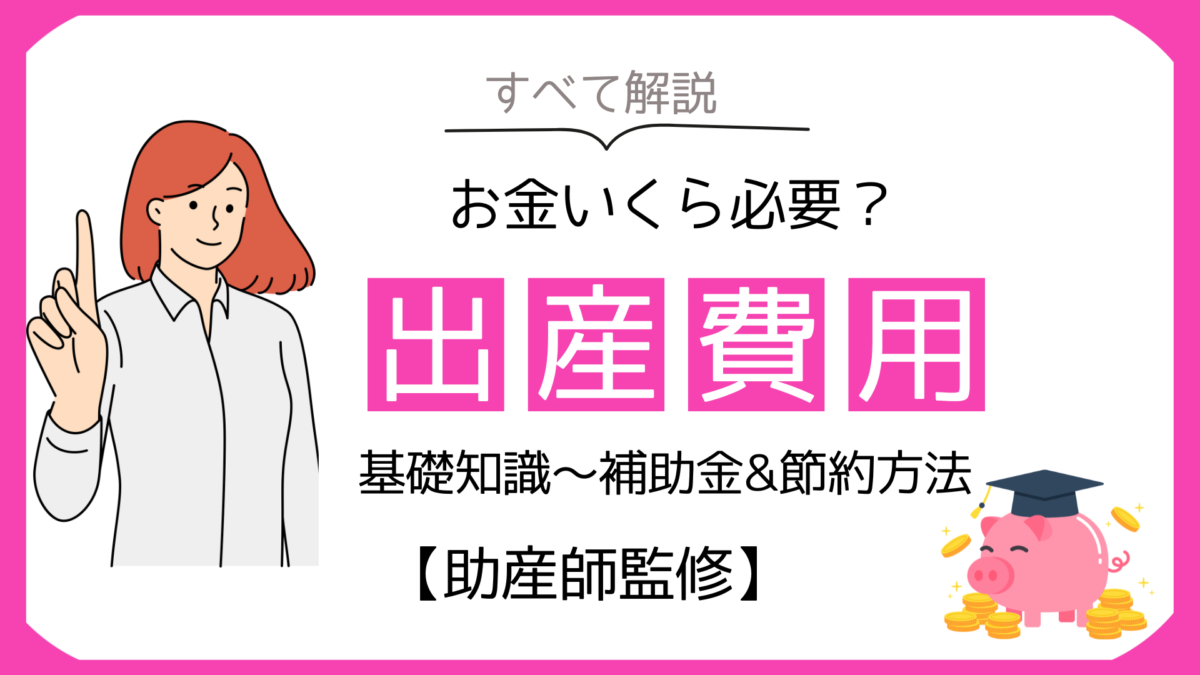
コメント