「母乳が思うように出ない…」そんなとき、不安や戸惑いを感じるのは自然なことです。
産後すぐの母乳分泌は、ホルモンの働きによって始まります。このホルモンの分泌は、赤ちゃんが乳首を吸う刺激によって活性化されます。つまり、授乳の回数やタイミング、ママの体調や心の状態が、母乳の出に深く関わっているのです。
本記事では、母乳が出にくいと感じたときに考えられる原因と、すぐにできる対処法をわかりやすくご紹介します。さらに、どうしても母乳だけでは足りないときのミルク補足の方法や、母乳外来など専門家の力を借りる選択肢についてもお伝えします。
この情報は、現場で多くのママたちを支えてきた助産師の視点も取り入れて構成しています。母乳育児に不安を感じている方も、きっと安心して読んでいただける内容です。無理をせず、赤ちゃんとママのペースで進めていきましょう。
*当サイトは、プロモーションを含みます
母乳を出す身体の仕組み

ホルモンの働き
母乳は、ママの体の中で分泌されるホルモンの働きによって作られます。特に重要なのが 「プロラクチン」 と 「オキシトシン」 という2つのホルモンです。この2つのホルモンが協力し合って、母乳育児を支えています。
プロラクチン
脳の下垂体から分泌されるホルモンで、母乳の分泌と維持に必須なホルモンです。
プロラクチンの濃度は、分娩直後が最も高く、その後徐々に低下していきますが、乳頭刺激(赤ちゃんが授乳の際に乳頭を吸う刺激)があると、その刺激のたびに一過性に上昇します。
授乳で赤ちゃんが乳頭をくわえて吸う(乳頭刺激)⇒ママの脳下垂体に「母乳作って~」と刺激が伝わる⇒プロラクチンが分泌される⇒母乳が産生される という仕組みになっています。
母乳量を向上させたいときに、1日に8回以上の授乳をすると母乳が出やすくなるというのは、1日8回以上の乳頭刺激によって、プロラクチン濃度が低下しにくくなるため母乳に適した状態が維持されるためです。
オキシトシン
脳の下垂体から分泌されるホルモンで、射乳反射(母乳が押し出される)を起こす役割があります。この射乳反射が起こることで、乳腺の周りの筋肉がぎゅっと縮まり、母乳がスムーズに赤ちゃんの口に届くようになります。
オキシトシンは、赤ちゃんの泣き声をきいたり、赤ちゃんのことを考えたりするだけでも射乳反射を起こすことがあり、授乳前にオムツを替えているだけで乳房全体がキュ~っとなる間隔を覚えたり、よその赤ちゃんが泣いてる泣き声をきいてもジワ~っと母乳が分泌されることもあります。
別名「しあわせホルモン」「愛情ホルモン」とも呼ばれ、このホルモンが分泌されることでストレスが軽減されたり、幸福感をえられたり、安心感をもたらす効果があることでも知られています。
このホルモンの分泌が、母乳育児を支えています。
授乳によるホルモンへの刺激
赤ちゃんが乳首を吸うことで、ママの脳が刺激され、ホルモン分泌が促されます。吸わせる回数が多いほど、母乳の分泌が安定しやすくなります。
母乳が出ない原因

母乳が出にくいと感じるのは、珍しいことではありません。主な原因はこちらです。対処法は後述します。
授乳回数が少ない
母乳は、赤ちゃんが乳首を吸う刺激によって「プロラクチン(乳汁分泌ホルモン)」や「オキシトシン(射乳ホルモン)」が分泌され、作られる仕組みになっています。
授乳回数が少ないとこの刺激が足りず、脳が「母乳はそんなに必要ない」と判断し、母乳の分泌量を減らしてしまいます。
特に、生まれてすぐの時期は、頻繁な授乳によって乳腺が刺激され、分泌能力が高まっていきます。逆に刺激が少ないと、母乳の分泌が軌道に乗らず減少していきます。
赤ちゃんの吸いつきが悪い
ママが頑張って授乳をしていても、うまく赤ちゃんの口に乳輪部まで含むことができず適切に吸いつけていなかったり、赤ちゃんが寝がちで授乳の際にも十分に吸えていないということがあります。
うまく吸えていないと、赤ちゃんが乳首を吸う刺激によって「プロラクチン(乳汁分泌ホルモン)」や「オキシトシン(射乳ホルモン)」が十分に分泌されません。
対処法も後述するので安心してくださいね。
ストレスや疲労がたまっている
ストレスや疲労がたまると、ホルモンの分泌がうまくいかなくなり、母乳が出にくくなることがあります。心や体が緊張していても、母乳がスムーズに出ないことがあります。
といっても、赤ちゃんのいるママは忙しく疲れているし、自分の時間も取れずストレスもあるもの。
水分が不足している
母乳は水分が多いため、水分不足は母乳不足に直結します。実は、母乳の約90%は水分。だから、ママの体の中に水分がしっかりないと、母乳を作るための材料が足りなくなってしまいます。
水分が不足してくると、体はまず「脳」や「心臓」「腎臓」など、命にかかわる大切な部分を優先して水分を送ろうとするので、母乳を作るための水分は後回しになり、母乳の出が悪くなってしまうことがあります。
ママは忙しくて、自分の水分摂取なんて後回しにしてしまいがちですが、喉が渇く前にコップ一杯飲む癖をつけましょう。子どもが小さい間は適温ですぐ飲めるウォーターサーバーがあると超便利です。

食生活が偏っている
妊娠中だけでなく、「授乳中も食事に気をつけましょう」とよく言われますね。それは、ママの食事が母乳の質や出方に関係しているからです。
母乳はママの血液から作られていて、その血液は毎日の食べ物から作られています。つまり、バランスのよい食事が、母乳づくりの土台になるというわけです。
栄養が足りないと、母乳の材料がそろわない
たとえば、野菜やたんぱく質が不足していたり、油っこいものや甘いものばかりになっていたりすると、母乳を作るための栄養が足りなくなってしまいます。
特に不足しがちなのは、以下のような栄養素:
- たんぱく質(肉・魚・豆腐・卵など)
- 鉄分(レバー・ひじき・ほうれん草など)
- カルシウム(牛乳・小魚・小松菜など)
- ビタミン・ミネラル(野菜・果物)
これらが不足すると、母乳の分泌量が減ったり、ママ自身が疲れやすくなったりして、結果的に授乳がつらくなってしまうことも。
慣れない育児でゆっくりする時間もない間は、惣菜や宅配などを上手に利用するのもありです。罪悪感は感じなくていい。賢く利用して、ご自身の栄養バランスも整えましょう。それが結果として赤ちゃんのためにもなります。
“徹底的に添加物不使用”のお惣菜をご自宅に保存料や化学調味料が無添加なのと、一度の宅配で30~70品目の食材が使用されているので栄養バランスも摂りやすく、私が気に入ったのは冷凍ではなく冷蔵という点。軽く温めるだけでよく、少し取り分けて夫のお弁当にも入れたりします。
おすすめポイントは、美味しいのはもちろんですが、買い物へ行かなくていい、調理しないので洗い物も激減。料理に取られる時間が圧倒的に減ることがメリットです。
毎回利用しなくてもOK!スキップもできるので、気になったら試してみてくださいね。
お子様にも安心!”添加物不使用”のつくりおきおかず母乳が出ないときの対処法
焦らず、以下を試してみましょう。
正しい授乳姿勢を保つ

姿勢と母乳と関係ある?と言われそうですが、大ありです。
授乳姿勢が合っていないことが原因で母乳分泌が悪くなっていることがあります。赤ちゃんが乳首を浅くくわえていたり、ママの身体が緊張していたりすると、うまく吸啜刺激(吸う刺激)が伝わらず、母乳を作るホルモンの分泌が十分に促されません。
また、不自然な姿勢での授乳は、肩こりや腰痛の原因にもなり、ママの疲労がたまりやすくなります。リラックスして授乳できる環境を整えることが、母乳育児の第一歩です。
姿勢を整えるポイント
ママの体をしっかり支える
- 背もたれ付きの椅子やクッション、授乳クッションなどを使い、背中をしっかり支えましょう。
- 足元にはフットレストや低めの台を置くと、膝の位置が安定し、長時間の授乳もラクになります。
赤ちゃんの体をママに密着させる
- 赤ちゃんの頭・肩・お尻が一直線になるように抱っこします。
- 赤ちゃんの体をママのお腹にぴったりくっつけ、「おへそ同士が向かい合う」ようにすると自然に深く吸いつけます。
授乳クッションを活用する
- 腕で赤ちゃんを支えるのがつらいときは、授乳クッションを使うと安定しやすくなります。
- 赤ちゃんの頭の位置が乳首と同じ高さになるように調整しましょう。
授乳クッション
dacco(産院で選ばれるメーカーNo.1)の授乳クッションです。
しっかり厚みがあるので、赤ちゃんの身体を持ち上げたりしなくても、上にドンと寝かせて授乳できるので、ママの負担軽減できます。
すぐにへたって、厚みのなくなる授乳クッションも多いなか、daccoのものはへたりが少ないのでオススメ。
へたらないというのは、結構重要なポイントで、赤ちゃんはどんどん成長して体重増えるのに、授乳クッションがへたってしまうと、重くなった赤ちゃんをママが支えてあげないといけなくなるので、ママの負担激増で腱鞘炎などになってしまう方もおられます。
丸洗いできるのもおすすめポイント。毎日使用するもの、清潔に使用できるのも大切なポイントになりますね。
ママが無理ない楽な体勢で赤ちゃんを支えて授乳できるよう、クッションなどを利用しながら行うのがポイントです。
姿勢が合っているか確認するサイン
- 赤ちゃんが口を大きく開けて、深くくわえている
- 授乳中にママが痛みを感じない
- 赤ちゃんのほっぺがふくらんでいて、ゴクンゴクンと飲み込む音がする
- ママの首・肩・背中が無理なくリラックスできている
授乳回数を増やす

母乳が足りていないかも…と感じたとき、授乳回数を増やすことはとても効果的な方法のひとつです。おっぱいに吸われる刺激があることで、脳から「もっと母乳を作って!」という指令が出て、母乳の分泌が促進される仕組みになっています。
以下に、自然に授乳回数を増やすためのポイントをご紹介します。
1. 「赤ちゃんのペース」に合わせてこまめに授乳
- 決まった時間にこだわらず、泣いたら・ぐずったら・口を動かしたらすぐ授乳
- 1日8回以上(できれば10回〜12回ほど)が目安です
- 昼だけでなく、夜間の授乳もとても大切!(夜は母乳を作るホルモンが特に出やすい時間帯)
🐣 2. 片方だけでなく「両方の胸」を吸わせる
- 片方が終わったらもう片方も飲ませて、両方の胸にしっかり刺激を
- もう一巡(左右で2回ずつ)してもOK!
- 「しっかり吸ってもらう」ことが、母乳づくりにつながります
💕 3. 授乳以外でもスキンシップを増やす
- 抱っこ、おんぶ、添い寝など、赤ちゃんとのふれあいが脳にやさしく刺激を与えます
- リラックスできる時間が増えると、母乳の出にもよい影響が
🌙 4. 夜間授乳を取り入れる
- 夜10時〜夜中2時ごろは、母乳を作るホルモン「プロラクチン」が最も出やすい時間帯
- 赤ちゃんが寝ていても、夜間にしっかり授乳するのがおすすめ(搾乳でもOK)
5.搾乳でもOK!
赤ちゃんに吸われるのが痛くて辛い場合や、思うように吸ってくれない場合は、直接授乳して吸ってもらうことにこだわらくても大丈夫。搾乳でもOKです。搾乳も手で行ってもいいし、搾乳器利用でもどちらでもいいので、やりやすいほうでしてみましょう。電動搾乳器で両方の乳房から同時に搾乳できるものもあり、両方からの同時搾乳は効果が高かったりします。
搾乳に興味がある方は、搾乳に関する次の記事も参考にしてください。
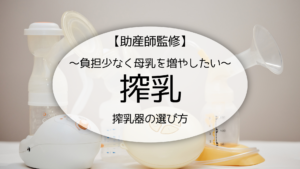
無理せず、できるところからで大丈夫
母乳の量は、赤ちゃんの成長やママの体調によって日々変化します。大切なのは、「少しずつ刺激を増やす」ことと、「ママがリラックスして取り組む」こと。
授乳回数を意識しすぎてストレスになってしまっては逆効果。
「今日はちょっと多めに吸わせた」「今日は多めに搾乳した」そのくらいの気持ちでOKです🌷
食生活を見直す

母乳はママの体の中で作られており、ママの食生活が母乳の質や量に大きく関わっているのです。バランスの良い食事を心がけ、鉄分・カルシウム・たんぱく質を意識的に摂りましょう。
主食・主菜・副菜をそろえよう
和食の基本である「一汁三菜」を意識すると、自然とバランスが取れます。
- 主食(ごはん・パン・麺など):エネルギー源として重要
- 主菜(肉・魚・卵・大豆製品など):母乳の材料となるたんぱく質
- 副菜(野菜・海藻・きのこなど):ビタミン・ミネラル・食物繊維を補給
母乳を作るのに役立つ食材
以下のような食材は、血行を良くして母乳分泌をサポートするといわれています。
- 根菜類(にんじん、ごぼう、大根など):体を温め、血流を促進
- たんぱく質豊富な食品(鶏ささみ、豆腐、納豆など):母乳の材料に
- 良質な脂質(ごま油、オリーブオイルなど):ホルモンバランスの維持に
カルシウムと鉄も意識して
母乳で赤ちゃんに栄養が送られるため、ママの体内からカルシウムや鉄が失われやすくなります。
- カルシウム:牛乳・ヨーグルト・小魚・小松菜など
- 鉄分:赤身の肉・レバー・ひじき・納豆など
バランスよく、無理なく取り入れて
もちろん、完璧な食事を毎日続けるのは難しいもの。大事なのは、「できる範囲で」「少しずつ意識してみること」です。意識するだけで違います。
コンビニや冷凍食品、外食なども上手に取り入れながらでOK!
- ごはん+お味噌汁+おかず(たんぱく質+野菜)を基本に
- コンビニや冷凍食品も、組み合わせでバランスをとる
- おにぎり+野菜スープなど、シンプルでもOK!
- 外食もジャンクフードよりは、定食系を意識!
栄養がしっかりとれていれば、ママの体調も整いやすくなり、母乳もスムーズに作られやすくなります。
手軽に食事バランスととのえちゃお♫
手軽に食事バランスを摂る方法としては、1食だけでも具だくさん味噌汁や野菜スープなどを取り入れるのがおすすめです。味噌汁やスープにすることで一度にたくさんの野菜が摂れ、あたたかいものを摂取することで、夏でも冬でも血流をよくします。血流よくする=母乳の分泌UPです。
一度にたくさん作って冷凍しておいてもいいし、子育てに忙しい今だけ宅配を利用するのもおすすめ。野菜たっぷりスープをチンするだけで、たっぷり栄養摂取!
ヒルナンデス!やZIP!、王様のブランチ、よじごじなど200以上の媒体で紹介されているGreenspoon(グリーンスプーン)が手軽で美味しいので案内しておきます。下記リンクから初回限定1食499円(税込539円)覗いてみてくださいね。最短4日で届きます。
ゴロゴロ野菜でカラダを喜ばせるならGreenspoon母乳が出にくい体質である
まれに体質的に分泌が少ないママもいます。胸が張らない、赤ちゃんが吸っても出ている感じがしない…。そんなとき、「自分のせい?」と責めてしまう方も少なくありません。
でも、それはママのせいではありません。ホルモンのバランス、体質、ストレス、出産時の状況など、さまざまな要因が関係しています。
ミルクを使うのは悪いことじゃない
母乳が思うように出なくても、赤ちゃんはミルクでしっかり育ちます。大切なのは「赤ちゃんが元気に育つこと」と「ママが笑顔でいられること」。
母乳にこだわりすぎず、自分らしい育児スタイルを見つけていきましょう。
十分に休息する
体を休めることでホルモンバランスも整いやすくなります。母乳は、ママの「こころ」と「からだ」からつくられます。過労や睡眠不足、ストレスがたまると、母乳を作るホルモン(プロラクチン)や、母乳を押し出すホルモン(オキシトシン)の分泌が低下しやすくなります。
授乳に追われて「寝る時間がない」「ごはんもゆっくり食べられない」という日々が続くと、体はどんどん緊張状態に…。そんなときは思い切って、家事を手放してみましょう。
「頑張らなきゃ」と思う気持ちはとても素敵ですが、すべてを一人で抱え込まなくて大丈夫。パートナーや家族、サポートサービスなど、頼れるものには頼ってみましょう。
- 赤ちゃんが寝たら一緒に横になる
- 一日一回は湯船に浸かってリラックス
- 家事は「やらない日」をつくる
- 頑張っている自分に「よくやってるよ」と声をかけてあげる
「母乳が足りない=自分の努力不足」ではありません。ママの体と心がリラックスすると、自然と母乳が出やすくなることも多いです。
育児は長い旅です。疲れたときは、立ち止まって深呼吸してみましょう。ママが元気でいることが、赤ちゃんにとって一番の栄養になります。
水分を補給する

無理にたくさん飲む必要はありませんが、「ちょこちょこ飲む」を習慣にしておくと、母乳もスムーズに出やすくなりますよ。
赤ちゃんのお世話に忙しく頑張ってるママは、自分自身のことは後回しにしてしまうことが多いです。でも、水分摂取は身体の基本!ママが元気なことが大切です!
「のどが渇いたな」と思ったときには、すでに体は水分不足気味かも。授乳中はいつも以上に水分が必要になるので、こまめに水分をとることがとっても大切です。
- おすすめの飲み物:白湯、麦茶、ノンカフェインのハーブティーなど
- NGになりやすい飲み物:カフェイン・アルコール(大量摂取は控える)
たとえばこんなふうに意識してみてください
- 1時間に1回くらいはコップ1杯の水やお茶を飲む
- 室内を立って動く際には水分をとる
- お風呂上がりや寝起きに水分をとる
- 夏場や汗をかいたときは、いつもより多めに
手の届くところにペットボトルで手軽に飲めるように置いておいたり、ウォーターサーバーもおすすめです。
赤ちゃんがいる間だけでもウォーターサーバーがあると便利です!ママがサッと水分を摂れるほか、赤ちゃんのミルクを作る際の時間短縮ができたり、離乳食作りにも役立ちます。赤ちゃんのミルクにウォーターサーバーを使用する際には、適した水を選ぶ必要があるので次の記事も参考にしてください。
⇒赤ちゃんとの生活を快適にするウォーターサーバーで押さえるべきポイント

おっぱいマッサージする
母乳が出にくいと感じたら、やさしくおっぱいをマッサージしてみましょう。乳腺の流れをよくし、母乳の分泌を促す効果があります。授乳前に軽くマッサージすることで、乳首が柔らかくなり赤ちゃんが吸いつきやすくなるメリットも。
マッサージのポイントは、強く押さず、やさしく円を描くように行うこと。お風呂上がりなど、身体が温まっているタイミングがおすすめです。
無理をせず、痛みがある場合は中止しましょう。自己流で不安なときは、助産師や母乳外来に相談するのが安心です。
どうしても母乳が出ないときの対処法

母乳が出るよう対処しながらも、まだ十分に母乳分泌がない間は次のこともおこなってみましょう。
搾乳器を利用する
乳房への刺激になり、母乳分泌を促します。直接授乳して吸ってもらうことにこだわらくても大丈夫。搾乳も母乳です、直接飲んでもらっても、搾乳でも栄養は変わりません。
搾乳は手で行っても、搾乳器利用でもどちらでもいいので、やりやすいほうでしてみましょう。電動搾乳器で両方の乳房から同時に搾乳できるものもあり、両方からの同時搾乳は効果が高いので考慮してみるのもオススメです。
搾乳で母乳の分泌量が増えてくると、赤ちゃんも楽に飲めるようになり、しっかり飲んでくれるようになります。しっかり飲んでくれるようになると、搾乳しなくても母乳量もしっかり保たれるので良いサイクルに入ります!
搾乳に興味がある方は、搾乳に関する次の記事も参考にしてください。
搾乳どうする?搾乳器の使用はどうすればいい?搾乳器に関する記事はこちら
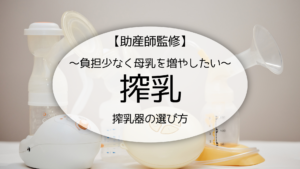
ミルクを併用する
母乳だけで量が不足している場合は、分泌量が追いつくまで、搾乳またはミルクを補足しましょう。赤ちゃんの栄養をしっかり補えます。
母乳だけの育児を目指すなら、ミルク補足をする場合は足しすぎないように気を付けましょう。
ミルクは母乳より消化に時間がかかります。ミルクをたっぷり飲ませて、赤ちゃんがたっぷり寝てしまうと、母乳を飲んでほしい時間に起きてくれません。起きてくれないと母乳までの時間が開いてしまい、あまり母乳の時間が開くとママの体は脳が〝あれ?母乳あまり作らなくていい?”と母乳量を減らしてしまいます。
母乳がたまっていなくてもドンドン吸われることで、ママの脳は〝もっと母乳作らなきゃ!”と母乳を作る指令を出すので母乳と母乳の時間を開けすぎないのがポイントです。1日8~10回以上は母乳または搾乳で刺激しましょう。
もしミルクを飲ませすぎて、母乳の時間に起きてくれない場合は搾乳でもいいので行ってください。搾乳を行うことで、〝もっと母乳作って”という指令をママの脳へ送りましょう。
母乳外来を受診する
専門家に相談することで、原因や対処法が具体的にわかります。出産した産院でみてもらえるなら産院でいいですが、あまり母乳に力を入れていない産院もあるのが事実です。
【できれば母乳で育てたい!】【母乳量を増やしたい!】と本気で考える場合は、助産院に問い合わせてみてください。助産院であれば、母乳の分泌が軌道に乗るまで、助産師がしっかりケアをしていることがほとんどです。
母乳が出ないときによくある質問
母乳はいつからいつまで出る?
一般的に、産後すぐから分泌が始まり、赤ちゃんが吸うことで分泌が続きます。離乳食が進むと徐々に減っていきますが、個人差があります。
母乳が安定するまでの期間はどのくらい?
産後1〜2か月程度で安定してくることが多いです。それまでは焦らず授乳を続けましょう。
まとめ
母乳の出は、ホルモンや授乳の回数、ママの体調など様々な要因に左右されます。
大切なのは「赤ちゃんに愛情をもって向き合うこと」。母乳でもミルクでも、赤ちゃんにとって一番はママの笑顔です。無理せず、必要なときは専門家の力を借りましょう。

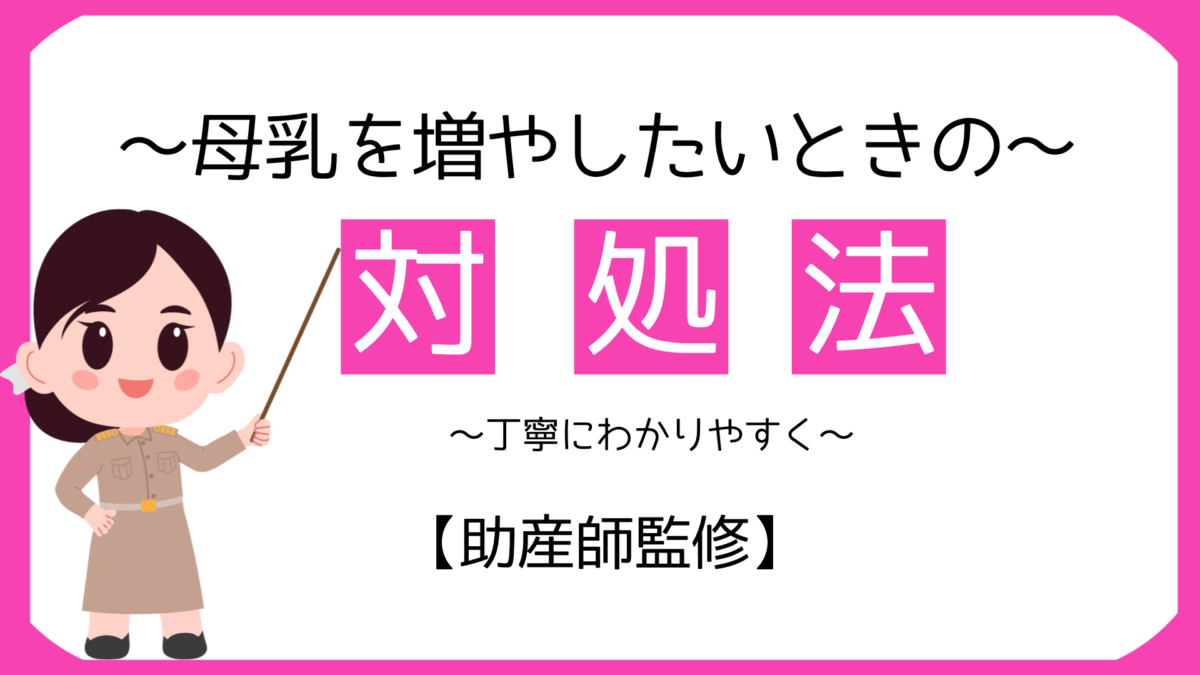

コメント