出産後に必要な手続きはたくさんありますが、事前に準備しておくことでスムーズに進めることができます。
この記事では、出産後に必須の手続きや必要書類、申請方法など、忙しいママやパパが困らないようにわかりやすく解説します。
「出産後の手続きって何が必要?」「どんな書類を準備すればいいの?」という方も安心して進められるよう、簡単にまとめました。
赤ちゃんとの新しい生活を、もっと楽に、もっと安心して始めるための参考にしてください!
*当サイトは、プロモーションを含みます
出産後に必要な手続き

次のような手続きが必要になります。提出期限や必要書類、提出方法などの詳細は、次の項で一つずつ説明します。
| 手続き名 | 内容 |
|---|---|
| 出生届の提出 | 赤ちゃんが生まれたことを戸籍に記載する手続き。戸籍が作られ、住民票などの行政サービスが受けられるようになる。 |
| 児童手当の申請 | 子どもを養育する家庭に支給される手当。申請により、子どもの年齢に応じた金額が毎月支給される。 |
| 健康保険の加入手続き | 赤ちゃんを健康保険に加入させる手続き。医療機関受診時に保険証が使用できるようになる。 |
| 出産育児一時金の受給申請 | 出産にかかる費用の一部を補助する制度。健康保険に加入していれば原則申請可能。 |
| こども医療費助成制度の申請 | 医療費の自己負担分を助成する制度。自治体によって内容は異なるが、申請で医療費負担が軽減される。 |
| 出産手当金の申請 | 働くママが産休中に収入を補うための給付金。健康保険の被保険者であることが条件。 |
| 育児休業給付金の申請 | 育児休業中のパパ・ママを支援する給付金。雇用保険に加入していることが主な条件。 |
出産後の出生届の手続き方法
赤ちゃんが誕生したら、まず行う大切な手続きが「出生届」の提出です。
出生届を出すことで、赤ちゃんの戸籍が作られ、住民票が登録されるようになります。
出生届を提出することによって、健康保険への加入や児童手当の申請など、さまざまな行政サービスを受けられるようになります。
提出には期限や必要な書類があるので、赤ちゃんが生まれたらできるだけ早めに準備しておきましょう。
提出期限
出生から14日以内(出生の日を含む)
必要書類
- 出生届(出生証明書が記載されたもの)※病院で記入
- 母子健康手帳
- 届出人の印鑑(※自治体によっては不要)
提出方法
市区町村役場の戸籍担当窓口へ直接提出
出産後の児童手当の申請方法
児童手当は、子どもを育てる家庭を支援するために支給される手当です。
申請することで、子どもの年齢に応じた金額が毎月支給され、子育てにかかる費用の助けになります。
手続きには期限があり、必要な書類もいくつかあるため、赤ちゃんが生まれたら忘れずに早めに申請しましょう。
申請期限
出生した翌日から15日以内(なるべく早めに)
必要書類
- 認印
- 請求者(保護者)の本人確認書類(運転免許証など)
- 健康保険証(会社員などの被用者の場合)
- 振込口座がわかる通帳やキャッシュカード
- マイナンバー(請求者・配偶者・児童)
提出方法
お住まいの市区町村役場の児童手当担当窓口へ提出(自治体によっては郵送での申請が可能なところもありますので、事前に確認しておきましょう。)
出産後の健康保険の加入手続き方法

赤ちゃんが生まれたら、健康保険にも加入する手続きが必要になります。
健康保険に入ることで、医療機関を受診する際に保険証が使えるようになり、自己負担額が軽くなります。
手続き方法は、保護者の働き方によって違ってくるので、自分がどちらに当てはまるかを確認して、早めに進めましょう。
社会保険の場合(会社員・公務員などの場合)
提出先:
勤務先(会社)の人事・総務担当部署
※そこから健康保険組合または協会けんぽに申請してもらいます
提出期限:
出生から14日以内(目安)
※保険証が発行されるまで医療費は一時立て替えになるため、できるだけ早く
必要書類:
健康保険被扶養者(異動)届
赤ちゃんの出生届出済証明書または住民票
世帯全員の住民票(必要な場合あり)
扶養者(親)の健康保険証の写し
所得証明(状況に応じて)
国民健康保険の場合(自営業・フリーランス・無職の人など)
提出先:
お住まいの市区町村役場の「国民健康保険担当窓口」
提出期限:
出生から14日以内(住民票作成後すぐ)
必要書類:
国民健康保険証(親の)
母子健康手帳
赤ちゃんの住民票または出生届出済証明書
印鑑(自治体によっては不要)
世帯主・保護者のマイナンバー確認書類と身分証明書
✍ ワンポイントアドバイス
- 加入後、保険証が発行されるまでに1〜2週間かかることがあります。
→ それまでに病院を受診した場合は、いったん全額自己負担で支払い、保険証が届いたら払い戻し請求できます。 - 「こども医療費助成制度」の申請は、健康保険証が必要になることが多いため、セットで早めに進めるとスムーズです。
出産育児一時金の受給申請

出産育児一時金は、出産にかかる費用の負担を軽くするために支給される制度です。
健康保険に加入していれば申請でき、まとまった金額が受け取れるので、出産費用の大きな助けになります。
申請方法や必要書類は加入している健康保険によって少し違うことがあるので、事前に確認しておきましょう。
申請期限
出産後できるだけ早く(医療機関へ事前に手続きする場合も)
必要書類(健康保険により異なる)
加入している健康保険に出産前に確認しておきましょう
- 申請書(出産育児一時金支給申請書)
- 出産費用の領収・明細書
- 母子健康手帳
- 健康保険証 など
提出方法
・健康保険組合(勤務先経由)または市区町村(国保の場合)へ提出
・または医療機関が直接受け取る「直接支払制度」もあり
こども医療費助成制度の申請
こども医療費助成制度は、子どもの医療費の自己負担分をサポートしてくれる制度です。
自治体によって対象年齢や助成の内容は少しずつ違いますが、申請しておくと病院での支払いがぐっと軽くなります。
申請した日から助成が適用される場合が多いため、赤ちゃんが生まれたら早めに手続きしておくと安心です。
申請期限
出生後できるだけ早く(医療費助成は申請後から対象になる場合あり)
必要書類
- 申請者の健康保険証
- 印鑑
- 子どもの出生届出済証明または住民票
- 振込先口座情報(自治体により異なる)
提出方法
市区町村役場の担当窓口で申請
出産手当金の申請
出産手当金は、出産後の収入をサポートしてくれる制度です。
働くママが産休中に収入が減るのを補うためのもので、出産手当金を受け取ることで、少しでも安心して育児に専念できます。
申請期限があるので、出産手当金の支給対象期間が終わったら、すぐに手続きを進めましょう。
申請期限
出産後、出産手当金の支給対象期間終了後すぐ
必要書類
- 出産手当金支給申請書(事業主と医師の証明が必要)
- 健康保険証
提出方法
勤務先を通じて、加入している健康保険組合に提出
育児休業給付金の申請

育児休業給付金は、育休中の生活費をサポートしてくれる助成金です。
育児休業を取得している間の収入を補填するため、ママやパパが安心して育児に専念できるように支援してくれます。
申請は、育休開始から1〜2か月以内に初回を行い、その後は原則として2か月ごとに申請が必要になります。
申請期限
育休開始から原則2か月ごとに申請(初回申請は開始から1〜2か月以内)
必要書類
- 育児休業給付金支給申請書
- 出生届の写しや母子手帳の写し
- 雇用保険被保険者証
- 賃金台帳や出勤簿など(勤務先が用意)
提出方法
勤務先を通じてハローワークへ申請
✅ 出産後の手続きチェックリスト【保存版】
| 手続き名 | 期限の目安 | 主な提出先 | 完了チェック |
|---|---|---|---|
| 🍼 出生届の提出 | 出生から14日以内 | 市区町村役場(戸籍係) | ☐ |
| 💰 児童手当の申請 | 出生翌日から15日以内 | 市区町村役場 | ☐ |
| 🏥 健康保険の加入 | 出生から14日以内 | 勤務先または市区町村役場 | ☐ |
| 🧾 出産育児一時金の申請 | 出産後すぐ | 健康保険組合 or 市区町村役場 | ☐ |
| 🩺 こども医療費助成制度の申請 | 出生後できるだけ早く | 市区町村役場 | ☐ |
| 🏡 出産手当金の申請 | 産休終了後できるだけ早く | 健康保険組合 | ☐ |
| 👶 育児休業給付金の申請 | 育休開始後1〜2ヶ月以内 | ハローワーク(勤務先経由) | ☐ |
🔖 アドバイス:市役所に行く際は、まとめて複数の申請ができる場合があるので、必要書類を持って一気に済ませるのが効率的!
出産後の手続きをスムーズに進めるコツ
必要な手続きを事前に把握する
出産後にやるべき手続きをスムーズに進めるためには、まず必要な手続きが何かをしっかり把握しておくことが大切です。
出生届や健康保険、育児手当の申請など、どれも重要ですが、手続きの期限や必要書類がそれぞれ異なるので、事前にリストアップしておくと安心です。
出産前に確認しておくだけで、赤ちゃんが生まれてから慌てずに済みます。
書類を事前に準備する
手続きに必要な書類を事前に準備しておくと、いざ手続きが必要になった時にスムーズに進められます。
例えば、母子健康手帳や住民票、健康保険証など、必要な書類がいくつかあります。
これらを出産前にチェックリストにして準備しておくと、手続きの際に「これが足りない!」と慌てることがなくなりますよ。
配偶者や家族と役割分担する
出産後は、何かと忙しくなり、赤ちゃんもいるためママは自由に動きにくくなります。配偶者や家族と協力して手続きを分担すると、とても効率的です。
たとえば、書類を取りに行く役割や、提出先を確認しておく役割を分けておくと、忙しい中でも負担を減らせます。
配偶者と一緒に話し合って、役割分担を決めておくと、出産後の手続きが格段にスムーズに進みます。
まとめ
出産後の手続きは、赤ちゃんのために必要な大切なステップです。事前に必要な手続きを把握し、書類を準備しておくことで、いざという時に慌てずに済みます。
また、配偶者や家族と協力して役割分担をすることで、手続きがスムーズに進み、負担も減らせます。
少しの準備と工夫で、忙しい育児生活を少しでも楽にできるので、ぜひ参考にしてみてください。
赤ちゃんとの新しい生活がより楽しく、安心して始められますように!
産後の手続きとともに、補助してくれる制度も利用して、産後の費用についても知っておきましょう。出産費用についてはこちら「出産費用」の記事を参考にどうぞ。
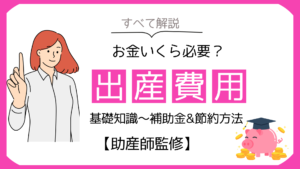

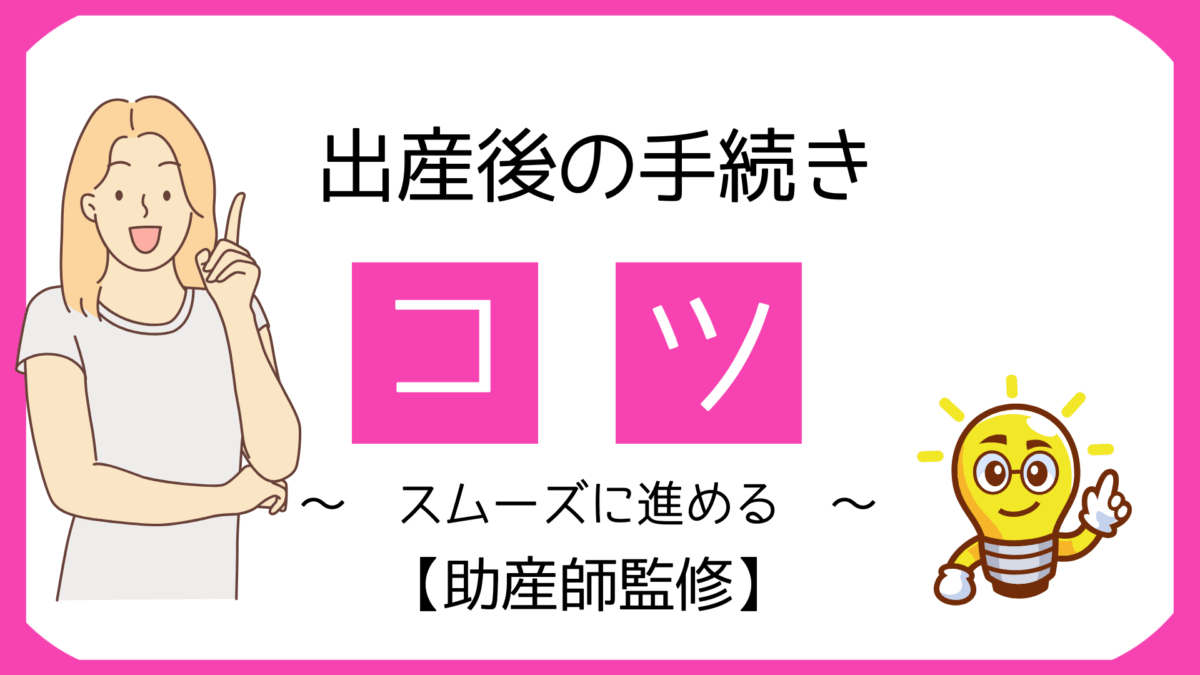
コメント